今回は、詐害行為取消権の定義、目的、行使要件、対象となる行為類型、法的効果、および行使期間の制限について、包括的かつ詳細に解説する。
詐害行為取消権の概要
詐害行為取消権は、民法第424条以下に規定される、債権者保護のための極めて重要な制度である。この権利は、債務者が自らの財産を不当に減少させる行為(詐害行為)を、債権者を害することを知りながら行った場合に、債権者がその行為を取り消し、散逸した財産を債務者の責任財産に回復させることを目的としている。
本権利は、債務者の財産処分に対する例外的な介入手段として機能する。本来、民法においては、個人が自身の財産を自由に処分できるという「財産不可侵の原則」が重要な柱の一つである。
しかし、この原則を無制限に適用すると、債務者が意図的に財産を隠匿したり、特定の債権者にのみ有利な処分を行ったりすることで、他の債権者が債権回収不能に陥る事態が生じ、債権者の正当な期待が裏切られる可能性がある。このような状況を防ぎ、債権者が強制執行を通じて債権を回収できる基盤を確保するために、詐害行為取消権が認められているのである。この制度は、債務者の財産処分の自由と、債権者の債権保全の期待という、二つの異なる法的価値の間の緊張関係を調和させるための法体系の努力を反映している。したがって、その行使には厳格な要件が課せられ、必ず裁判上の訴えによって行われる必要がある。
詐害行為取消権の基本
定義と目的
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知って自己の責任財産を積極的に減少させる法律行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為の取消しを裁判所に請求し、逸出した財産を債務者の責任財産に回復させる権利を指す。これは民法第424条1項に規定されており、「債権者取消権」とも称される。
本制度の主たる目的は、債務者の一般財産(責任財産)を保全し、債権者が強制執行を通じて債権を回収できる可能性を確保することで、債権者を保護することにある。債務者の一般財産は、一般債権者の共同担保としての役割を果たすため、その散逸を防ぐことは、債権者の「債務者の財産から債権を回収できるだろう」という期待を保護する上で不可欠である。例えば、AがBに1000万円の貸金債権を有していたにもかかわらず、唯一の資産である評価額800万円の自宅不動産を強制執行から逃れるために友人Cに200万円で譲渡した場合、BはAC間の不動産売買契約の取消しを請求し、土地をAの責任財産に戻すことで債権回収を図ることができる。
この権利は、必ず裁判上の請求によって行使される必要があり、内容証明郵便等による取消通知では法的な効力は生じない。
行使の要件
詐害行為取消権を行使するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要がある。
1. 被保全債権の存在と性質
債権者の債務者に対する債権(被保全債権)は、詐害行為が行われる「前」の原因に基づいて成立していなければならない(民法第424条3項)。これは、本権利が債権者の「債務者の財産から債権を回収できるだろう」という期待を保護するために認められたものであるため、詐害行為後に債権を取得した者は、当該行為によって失われた財産からの債権回収を期待していないという考え方に基づく。この「期待保護」という理念は、本制度の根源にあるものであり、債権者が債務者の既存の財産状況を信頼して信用を供与するという経済的・法的現実を保護するものである。したがって、詐害行為後に発生した債権にまで取消権を認めると、取引の安全が害されることになる。例えば、不動産物権の譲渡行為が債権成立前になされた場合、その登記が債権成立後に経由されたとしても、詐害行為取消権は成立しないとされている。
被保全債権は、強制執行により実現可能なものでなければならない(民法第424条4項)。例えば、強制執行に付さない旨の合意がある債権や、訴訟を提起しない旨の特約がある債権は対象外となる。また、被保全債権は金銭債権に限られず、不動産や動産などの特定物債権も、詐害行為により債務者が無資力となる場合には取消権を行使できる。ただし、特定物債権の保全は、債務者の責任財産保全という制度趣旨から限定的に解される場合がある。抵当権等で担保されている債権の場合、債務者所有の不動産が目的であれば、被保全債権額が抵当目的物の評価額を超える部分に限って取消権を行使できる。一方、債務者以外の物上保証人の不動産が目的であれば、債権全額について行使可能である。
2. 債務者の無資力
債務者が、詐害行為時および取消権行使時(訴訟の事実審口頭弁論終結時)に無資力(財産よりも債務が超過している状態)であることが必要である。これは、債務者に十分な資力があれば、他の資産から債権を回収できるため、詐害行為取消という例外的な制度を用いる必要がないからである。一度無資力になっても、その後資力を回復した場合には、取消の必要性が失われる。債務者の無資力は、単なる計数上の債務超過だけでなく、債務者の信用力も含めて判断される場合がある。
債務者の無資力が詐害行為時だけでなく、取消権行使時にも必要とされることは、詐害行為取消権が「責任財産の保全」という目的を達成するための手段であることを明確に示している。
もし債務者が資力を回復していれば、もはや「保全」の必要性はなく、債権者は通常の強制執行手段で債権を回収できるため、過去の行為を取り消すという強力な手段を講じる正当性が失われる。これは、法制度が常に「必要性」と「実効性」を重視している表れであり、債権者に対して、債務者の財産状況を継続的に監視し、適切なタイミングで訴訟を提起するよう促す実務上のインセンティブとなる。
3. 財産権を目的とした行為であること
詐害行為取消権の対象は、財産権の変動を目的とした法律行為に限られる。これは、財産と無関係な行為を取り消したとしても、債務者の財産保全に繋がらないためである。
例えば、養子縁組、婚姻、離婚などの身分行為は対象外である。また、相続放棄も、財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げるに過ぎないため、詐害行為取消権の対象とはならないとされている。
財産権を目的とする行為に限定し、身分行為を除外する法的判断は、民法が個人の自由と尊厳に関わる身分関係の形成・変更を、債権者の利益よりも上位の価値として保護していることを示唆している。
相続放棄の例では、相続人が自らの意思で相続財産を取得しないことを選択する身分行為であり、これを債権者の都合で取り消すことは、個人の意思決定の自由に対する過度な介入とみなされる。この区分は、債権回収という経済的利益の追求が、個人の基本的な権利や自由を侵害しないよう、法が慎重にバランスを取っていることの表れである。
4. 債務者の詐害意思
債務者が、詐害行為の当時、その行為によって債権者を害すること(財産が減少し、返済ができなくなること)を知っていたこと(詐害意思)が必要である(民法第424条1項本文)。この要件は、債権者に損害を与えようとする積極的な意図(害意)までは不要であり、単なる「認識」で足りるとされている。
債務者の詐害意思について「害する意図」ではなく「認識」で足りるという判例法理は、実務における立証の困難性を考慮した結果である。積極的な害意は内心の事実であり、直接的な証拠を得ることは極めて難しい。これに対し、行為の結果として債権者を害することを知っていたという「認識」であれば、客観的な状況証拠(例えば、行為時の債務者の財産状況、行為の態様、受益者との関係性など)から推認することが可能になる。この要件の緩和は、債権者保護の実効性を高める一方で、債務者の財産処分行為が常に詐害意思の疑いをかけられる可能性があるという、取引の不確実性も生じさせる。
5. 受益者・転得者の悪意
詐害行為の相手方である受益者(詐害行為によって直接利益を受けた者)や、その受益者からさらに財産を取得した者(転得者)が、当該行為が債権者を害することを知っていたこと(悪意)が必要である。もし受益者や転得者が善意(知らなかった)であった場合は、その者を保護する必要があるため、取消権は成立しない。受益者や転得者の善意の立証責任は、原則として受益者または転得者自身に課せられる。
詐害行為取消権の要件一覧
| 要件 | 内容 | 詳細 | 関連条文/判例/改正点 |
| 被保全債権の存在と性質 | 詐害行為前の原因に基づく、強制執行可能な財産権を目的とした債権であること | 金銭債権に限らず特定物債権も可。不執行合意債権等は不可。債権発生原因が詐害行為前であること。 | 民法424条3項, 4項, 最判昭36.7.19 |
| 債務者の無資力 | 詐害行為時および取消権行使時に、債務超過の状態にあること | 他の資産から回収可能であれば不要。資力回復で取消不要。 | |
| 財産権を目的とした行為 | 財産権の変動を伴う法律行為であること | 養子縁組、婚姻、離婚、相続放棄などは対象外。 | |
| 債務者の詐害意思 | 債務者が行為により債権者を害することを知っていたこと | 「害する意図」までは不要、「認識」で足りる。 | 民法424条1項, 最判昭35.4.26 |
| 受益者・転得者の悪意 | 受益者や転得者が、債権者を害することを知っていたこと | 改正民法で転得者要件が厳格化。受益者・転得者が善意なら不可。立証責任は受益者・転得者側。 | 民法424条1項但書, 424条の5 |
詐害行為取消の対象となる行為類型
A. 典型的な詐害行為
詐害行為取消権の対象となる行為は多岐にわたるが、その中でも特に典型的なものとして以下の行為が挙げられる。
- 贈与
贈与は、債務者の財産を無償で減少させる行為であるため、債務者の責任財産を直接的に毀損し、債権者への弁済原資を失わせることから、最も典型的な詐害行為の対象となる。 - 廉価売買
市場価格よりも著しく低い価格での売買(不相当な価額での売却)も、債務者の財産を不当に減少させる行為として、詐害行為の対象となり得る。これは、実質的には贈与の要素を含むものと評価されるためである。
B. 改正民法における新たな類型と要件
1. 相当の対価を得てした財産の処分行為 (民法第424条の2)
債務者がその有する財産を処分し、受益者から相当の対価を取得している場合、原則として詐害行為にはあたらない。これは、財産の種類が変わるだけで債務者の総財産は減少せず、また、相当価格での処分行為を詐害行為取消しの対象とすると、取引の相手方を委縮させ、経済的に困窮している債務者の資金調達機会を奪うことを避けるためである。
しかし、以下の3つの要件をすべて満たす場合に限り、例外的に詐害行為取消請求が可能である。
- その行為が、不動産の金銭への換価など、財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(隠匿等の処分)をするおそれを現に生じさせるものであること。
- 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
- 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2. 既存の債務についての担保の供与または債務の消滅行為 (民法第424条の3)
債務者が法律上の義務に従って弁済を行う行為は、弁済の前後で債務者の財産に実質的な変化がないため、原則として詐害行為にはあたらない 。
しかし、以下の要件をすべて満たす場合に限り、例外的に詐害行為取消請求が可能となる(民法第424条の3第1項)。
- その行為が、債務者が「支払不能」(支払能力を欠くために、弁済期にある債務につき、一般的かつ継続的に弁済できない状態)の時に行われたものであること。
- 債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
また、弁済期が到来していない債務の弁済など、債務者の義務に属さない行為(非義務的行為)については、以下の要件をすべて満たす場合に取消請求が可能で(民法第424条の3第2項)。
- その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。
- 債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
3. 過大な代物弁済等 (民法第424条の4)
代物弁済は、債務の履行として行われるため、原則として詐害行為の対象とはならない。しかし、受益者の受けた給付の価額が、その行為によって消滅した債務の額より過大である場合、その消滅した債務の額に相当する部分以外の過大な部分についてのみ、詐害行為取消請求が認められる(民法第424条の4)。この場合、通常の詐害行為取消権の要件(民法第424条に規定する要件)を満たす必要がある。
過大な代物弁済の場合に「過大な部分」のみを取り消せるという規定は、法の合理性と公平性を追求した結果である。代物弁済自体は債務の履行として正当な行為であり、その全額を取り消すことは、受益者にとって不当な結果をもたらす可能性がある。しかし、債務額を超える部分については、債務者の責任財産を不当に減少させる行為と評価できるため、その部分に限り取消を認めることで、債権者保護と受益者の利益のバランスを図っている。これは、取引の本来の目的を尊重しつつ、不当な財産流出を是正するという、比例原則に基づいたアプローチである。
詐害行為取消の対象行為類型と要件の比較
| 行為類型 | 原則 | 例外的に詐害行為となる要件 | 関連条文 | 備考 |
| 贈与 | 典型的な詐害行為 | なし | 民法424条1項 | 債務者の財産を無償で減少させるため |
| 廉価売買 | 典型的な詐害行為 | なし | 民法424条1項 | 市場価格より著しく低い価額で財産を減少させるため |
| 相当対価を得てした財産の処分行為 | 原則として詐害行為ではない | 1. 隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせること AND 2. 債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたこと AND 3. 受益者が債務者の隠匿等の意思を知っていたこと | 民法424条の2 | 破産法との整合性を図るため、主観的要件を重視 |
| 既存債務の弁済・担保供与 | 原則として詐害行為ではない | 1. 債務者が支払不能時に行われたこと AND 2. 債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意図があったこと | 民法424条の3第1項 | 破産法上の偏頗行為否認の規律に準拠 |
| 非義務的行為(期限前弁済等) | 原則として詐害行為ではない | 1. 債務者が支払不能になる前30日以内に行われたこと かつ、 債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意図があったこと | 民法424条の3第2項 | 破産法上の偏頗行為否認の規律に準拠 |
| 過大な代物弁済等 | 原則として詐害行為ではない | 受益者の受けた給付の価額が消滅債務額より過大な部分について、他の詐害行為要件を満たす場合 | 民法424条の4 | 超過部分のみ取消しが可能、比例原則を反映 |
詐害行為取消権の行使と効果
行使方法と相手方
詐害行為取消権は、必ず裁判上の請求によって行使される必要がある。口頭や書面での意思表示では、法的な効力は生じない。訴訟の相手方(被告)は、詐害行為によって利益を受けた受益者、またはその受益者からさらに財産を取得した転得者である。債務者は、原則として被告にする必要はない。
しかし、債権者が詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく債務者に対して訴訟告知を行う義務がある。この訴訟告知は、判決の効力が債務者にも及ぶことから、債務者に訴訟に参加する機会を確保し、債務者の防御の機会を保障するための手続き的保障である。これにより、債務者の法的立場が直接的に影響を受ける場合に、適切な手続きが保障されることになる。
取消しの効果
詐害行為取消権が認められた場合、その効果は多岐にわたる。
1. 逸出財産の原状回復
詐害行為取消権の主要な効果は、債務者から逸出した財産をその責任財産に回復させることである。この原状回復は、まず詐害行為によって移転した財産権が債務者に当然に復帰する「観念的原状回復」の段階を経て、次に不動産の登記名義の回復や動産の引渡しを受けるといった「現実的原状回復」の段階で実現される。
現実的原状回復の方法には、財産の種類によって違いがある。動産や金銭の場合は、債権者は受益者や転得者に対して直接自己への引渡しを請求できる。一方、不動産の場合は、所有権移転登記の抹消や受益者から債務者への所有権移転登記手続を請求することになる。不動産が債権者に直接移転するわけではない点に留意が必要である。
また、現物での返還が困難な場合(例えば、財産が既に処分されている場合など)には、価額償還(金銭による賠償)を請求することができる。この場合の価額は、特別の事情がない限り、当該詐害行為取消訴訟の事実審口頭弁論終結時を基準として算定される。
この原状回復の仕組みは、詐害行為取消権が単に取引を無効にするだけでなく、債権回収という実効的な目的を達成するために、財産を債務者の責任財産に戻すという具体的な効果を持つことを示している。特に、金銭や動産については債権者への直接引渡しを認めることで、債権回収の迅速化を図っている。
2. 他の債権者および債務者への効力
詐害行為取消権を認める判決の効力は、訴訟の当事者(取消債権者と受益者・転得者)だけでなく、債務者および他の全ての債権者にも及ぶ(民法第425条)。
この規定は、詐害行為取消権が、個別の債権者による権利行使でありながらも、その効果が債務者の一般財産全体に影響を与え、他の債権者にとっても利益となるという集団的側面を持つことを明確にしている。これにより、一度詐害行為が取り消されれば、その財産は全ての債権者の共同担保として回復され、個別の債権者が再度同じ行為を取り消す訴訟を提起する必要がなくなるため、法的安定性と効率性が向上する。
3. 受益者・転得者の反対給付請求権
詐害行為が取り消された場合、受益者が既に反対給付(例えば、売買代金)を履行していた場合や、弁済行為が取り消された場合は、受益者は債務者に対して直接反対給付の返還請求権を取得し、また、弁済によって消滅していた債権が復活することが明記された(民法第425条の2、3)。これは、受益者が詐害行為に関与していたとしても、その財産を不当に失うことを防ぎ、債務者の不当利得を回避するための措置である。
転得者に対する詐害行為が取り消された場合も同様に、転得者は債務者に対して、自身の反対給付の額や弁済等によって消滅した債権額を限度として、受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権や弁済によって復活する債権額と同額の債権を有することが規定されている(民法第425条の4)。これらの規定は、詐害行為取消によって取引が遡及的に無効とされる結果、受益者や転得者が不利益を被ることを一定程度緩和し、公平な解決を図るものである。
行使期間の制限(除斥期間)
詐害行為取消請求に係る訴えは、以下の期間制限に従う必要がある(民法第426条)。
- 債権者が、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年を経過したとき。
- 行為の時から10年を経過したとき。
この期間制限は「出訴期間」とされており、消滅時効とは異なる性質を持つ。そのため、時効の更新(旧中断)や完成の猶予(旧停止)に関する規定は適用されない点に注意が必要である。
関連制度との比較
詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全するための唯一の制度ではない。債権者代位権や破産法上の否認権といった関連制度が存在し、それぞれ目的、要件、効果が異なるため、これらの制度との比較理解が不可欠である。
A. 債権者代位権との比較
債権者代位権(民法第423条以下)と詐害行為取消権は、いずれも債務者の責任財産を保全するという共通の目的を持つ。しかし、その機能と対象行為には明確な違いがある。
- 対象行為の性質: 詐害行為取消権が、債務者が自らの意思で積極的に財産を減少させる行為(例:贈与、売却)を対象とするのに対し、債権者代位権は、債務者が自らの権利(例:第三者に対する債権)を行使しないという「不作為」を対象とし、債権者が債務者に代わってその権利を行使するものである。
- 債務者の財産処分への干渉度: 詐害行為取消権は、債務者の財産処分行為そのものの効力を否定するものであり、債務者の財産処分の自由に対するより強い介入である。
- 回復の対象: 詐害行為取消権は、逸出した財産を債務者の責任財産に「回復」させることを目的とする。動産や金銭については、取消債権者が直接自己への引渡しを請求できる場合がある。一方、債権者代位権は、債務者に代わって権利を行使し、その結果得られた財産を債務者の責任財産に「帰属」させることを目的とする。金銭や動産については、債権者が直接自己に引き渡すことを求めることができる。
- 債務者の処分権: 改正民法により、債権者が債権者代位権を行使しても、債務者は被代位権利の取立や処分が妨げられず、第三債務者も債務者に返済することが認められるようになった。
債権者代位権と詐害行為取消権は、債務者の責任財産保全という共通の目的を持ちながらも、その行使の要件、効果、そして法改正による詳細な規律において、それぞれ異なる特徴を持つ補完的な制度である。債権者は、債務者の行為の性質(積極的な財産減少か、消極的な権利不行使か)に応じて、適切な法的手段を選択する必要がある。
詐害行為取消権、債権者代位権の比較
| 項目 | 詐害行為取消権 | 債権者代位権 |
| 目的 | 債務者の積極的な財産減少行為の取消し、責任財産の回復 | 債務者の権利不行使の代位行使、責任財産の保全 |
| 対象行為 | 債務者の財産減少行為(贈与、廉価売買、偏頗弁済等) | 債務者が有する権利(債権、物権等)の不行使 |
| 行使主体 | 個別債権者 | 個別債権者 |
| 要件 | 無資力、債務者・受益者の詐害意思/悪意等 | 無資力(原則)、被保全債権の存在、被代位権利の存在 |
| 行使方法 | 裁判上の請求のみ | 裁判外・裁判上 |
| 効果 | 詐害行為の取消し、逸出財産の債務者への回復(原則現物、例外価額) | 債務者に代わって権利行使、債務者の責任財産への回復 |
| 判決の効力 | 債務者および全ての債権者に及ぶ | 債務者にも及ぶ |
| 行使期間 | 知った時から2年/行為の時から10年(出訴期間) | (原則として時効の期間制限なし) |
主要な判例
遺産分割協議の対象性
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るとされている。これは、遺産分割協議が、相続開始によって共同相続人の共有となった相続財産の帰属を確定させる行為であり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であると解されるためである。債務者である相続人が、他の相続人との間で、自らの債権者を害することを知りながら、本来取得すべき相続分を放棄したり、極めて不均衡な分割を合意したりした場合に、債権者はこの遺産分割協議を取り消し、債務者の責任財産を回復させることが可能となる。
この判例は、遺産分割協議が身分行為の側面を持つ一方で、財産権の変動に直結する行為であるため、詐害行為取消権の適用範囲に含まれることを明確にした。これは、債務者が相続という機会を利用して財産を隠匿することを防ぐための重要な法的手段である。一方で、相続放棄は、財産を積極的に減少させる行為ではなく、相続人の意思決定に強く関わる身分行為であるため、詐害行為取消権の対象とはならない。
新設分割の対象性
株式会社の新設分割も、詐害行為取消権の対象となり得ると判断された判例が存在する。これは、債務超過状態にある会社が新設分割を行い、その対価として新設会社の株式を取得したとしても、その株式が債権者にとって保全、財産評価、換価が著しく困難なものであり、かつ、債務が新設会社に承継されずに分割会社に残された場合、実質的に債権者を害すると評価されるためである。
その他の重要判例
- 詐害行為取消訴訟と消滅時効の中断→債権者が受益者を相手どって詐害行為取消の訴えを提起しても、債権につき消滅時効中断の効力は生じないとされている。これは、詐害行為取消訴訟が債務者に対する債権の存否を直接争うものではないためである。したがって、債権者は、詐害行為取消訴訟とは別に、被保全債権の消滅時効を中断させるための措置を講じる必要がある。
- 受益者による消滅時効の援用→詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができる。これは、受益者が債権者の債務者に対する債権の消滅時効が完成していることを主張することで、詐害行為取消権の成立要件(被保全債権の存在)を否定できることを意味する。
- 債権譲渡の通知の対象性→債権譲渡の通知自体は、債務者の責任財産を減少させるものではなく、単に対抗要件に過ぎないため、詐害行為取消権行使の対象とはならない。
結論
詐害行為取消権は、債務者が債権者を害する意図をもって財産を不当に減少させた場合に、債権者がその行為を取り消し、債務者の責任財産を保全するための、民法上の重要な債権者保護手段である。
引用文献(2025年6月12日アクセス)
- 詐害行為取消権 Wikipedia
- Wikibooks 民法424条
- 第3 詐害行為取消請求権(債権者取消権)
- 2 債権者代位権、 詐害行為取消権
- Oh-Ebashi Newsletter, 改正債権法の詐害行為取消権
- 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | 最高裁判例一覧 意思表示等に関する判例 – 詐害行為/背信的悪意
- 詐害行為取消の範囲を狭める方向へ | アクティクス法務事務所 民法(債権法)改正|詐害行為取消権
- 詐害行為取消権 – ウィキバーシティ
- 筑波大学 法科大学院 詐害行為取消権の民法改正案の特質
- 詐害行為取消権 – 渡部一郎 法律事務所 民法(債権法)改正について(11) 第16 詐害行為取消権
- 国税庁 詐害行為取消権の見直し論について-国税徴収実務の観点から偏頗弁済を中心に-
- 詐害行為取消権・否認権における逸出財産の原状回復の構成・補論
- 金子総合法律事務所, 民法第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
- 債権法改正(1) 詐害行為取消権について
- 判例チェック No.42 最高裁判所第二小法廷平成24年10月12日判決平成22(受)622詐害行為取消請求事件
- 会社分割と詐害行為取消権 | 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京丸の内・横浜)
- 中京大学, 会社分割と詐害行為取消権
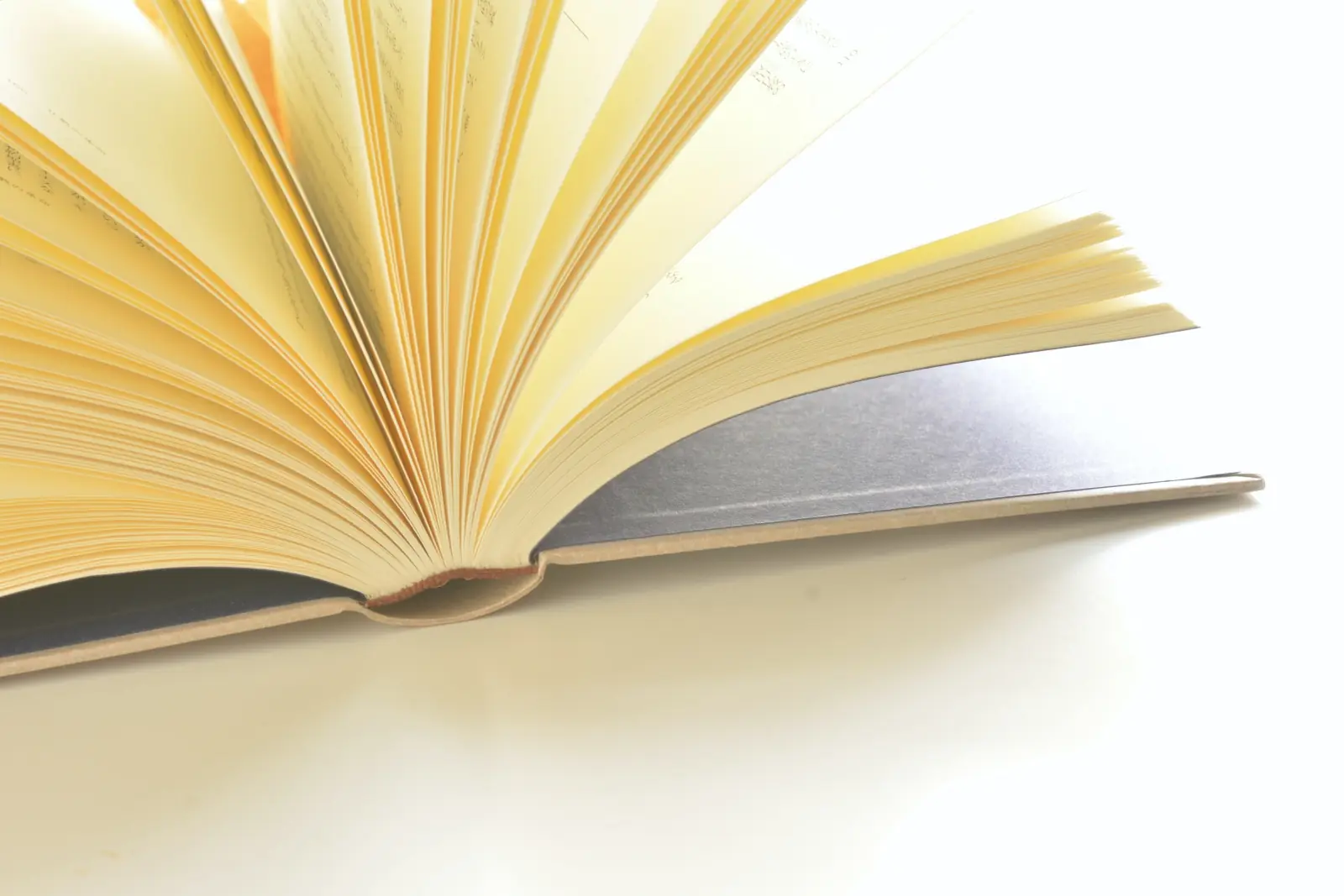

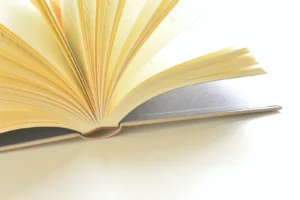
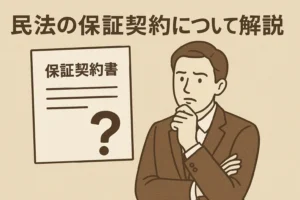


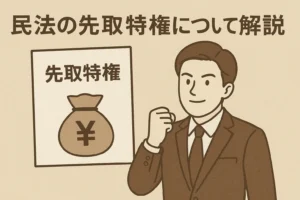
コメント