はじめに 不倫と「不貞行為」の法的違い
一般的に「不倫」という言葉は、配偶者以外の異性との親密な関係全般を指し、その範囲は個人の感覚によって曖昧です。しかし、法律の世界において、慰謝料請求や離婚の根拠となるのは、この一般的な「不倫」ではなく、「不貞行為」という概念です。
単なる感情的なつながりや異性との交流を超え、「自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」を主要な要件とします。
民法上の「不貞行為」は、昭和48年の最高裁判決において
「既婚者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。この行為は、民法第752条に規定されている夫婦間の「同居、協力及び扶助の義務」に含まれる「貞操義務」、すなわち配偶者以外と性的な関係を持たないという義務に違反するものです。
不貞行為は、この貞操義務の違反により、夫婦の婚姻共同生活の平穏という権利を侵害する行為とみなされ、民法第709条に定める「不法行為」に該当します。重要な点として、不貞行為は刑法に規定された犯罪ではないため、これを行ったとしても逮捕されたり、刑事罰を受けたりすることはありません。しかし、民法上の不法行為であるため、損害賠償責任、すなわち慰謝料の支払い義務が発生します。
「性的関係」の範囲と重要性
「不貞行為」の成立において最も中心的な要件は、「性的関係(肉体関係)」の存在です。この「性的関係」は、男女間の性交渉(性器の結合)に限定されず、口腔性交(オーラルセックス)などの「性交類似行為」も含まれるとされています。
性的関係の回数についても、たとえ1回のみの行為であっても不貞行為とみなされます。また、売春や買春といった行為も、原則として不貞行為に該当します。
「自由な意思」の原則
不貞行為が法的に成立するためには、その行為が当事者の「自由な意思」に基づいて行われたものであることが必須です。これは、行為者の自発的な選択がなければ、その行為に対する法的な責任を問うことができないという、法における基本的な原則に根差しています。
具体的には、強姦されたり、脅迫されたりするなどして、一方的に性行為を強要された被害者側には、不貞行為は成立しません。このような状況では、被害者は婚姻関係における貞操義務を自らの意思で破ったわけではなく、暴力や強制の対象となったため、法的な非難の対象とはならないからです。
婚姻関係の破綻の有無
不貞行為が不法行為とみなされ、慰謝料請求の対象となるのは、それが「平穏な婚姻関係を破綻させてしまうため」です。この原則に基づき、不貞行為が行われた時点で、既に夫婦関係が客観的に破綻しており、修復の見込みがないと判断される場合には、法的に保護すべき婚姻関係が存在しないため、不法行為にはあたらない可能性があります。
しかし、「破綻」の認定は厳格に行われます。単に夫婦喧嘩が多い、不仲であるといった事情だけでは、婚姻関係が破綻していたとは認められません。
客観的に婚姻生活が破綻していると判断されるには、例えば長期間の別居が続いていたなど、婚姻共同生活の実態が失われ、回復の見込みがないと評価される状況が必要です。
一方で、家庭内別居の場合、実際の夫婦関係の程度によって判断が異なりますが、同居している状況であれば、何らかの夫婦関係が成立しているとみなされ、不貞行為が不法行為に該当すると判断される可能性が高いと考えられています。
不貞行為とみなされない行為
「不貞行為」の法的定義は「性的関係」の有無が中心となるため、性的関係がない場合、原則として不貞行為とはみなされません。
例えば、異性とLINEやメールなどでやり取りをしていただけの場合、単にデートや食事をしただけの場合、あるいは手をつないだり、キスやハグをしただけの場合などは、原則として不貞行為には該当しないとされています。これらの行為は、道義的には問題視される可能性があっても、法的な「不貞行為」の要件である「性的関係」を満たさないためです。
しかし、これらの行為が肉体関係を強く示唆するようなやり取りを伴う場合や、後述する「例外的な不法行為」に該当する可能性も存在します。
例外的な「不法行為」の可能性
「不貞行為」は原則として肉体関係の存在を必須としますが、例外的に肉体関係の証拠が乏しい場合でも、慰謝料請求が認められる「不法行為」が存在する可能性があります。これは、単に性的な行為があったか否かだけでなく、婚姻共同生活の平和を侵害し、その破綻を決定的にしたと判断されるような、不倫相手による「強い働きかけや言動」があった場合に適用されます。したがって、性的関係がなくとも、不倫相手が積極的に夫婦関係に介入し、例えば頻繁な連絡や密会を重ね、離婚を要求するような言動によって、夫婦関係の破綻を意図的に引き起こしたと認められる場合には、その行為が「不貞行為に準ずる不法行為」として評価され、慰謝料の支払義務が発生することがあります。
不貞行為がもたらす法的効果
離婚原因としての不貞行為
不貞行為は、民法第770条に定められた「裁判上の離婚」原因の一つとして明確に位置づけられています。これは、配偶者が不貞行為を行った場合、その事実を理由として、他方の配偶者が裁判所に離婚を請求できる法的根拠となることを意味します。民法は、夫婦関係の破綻を招く特定の重大な事由を離婚原因として列挙しており、不貞行為はその中でも最も典型的なものの一つです。不貞行為の事実が証明されれば、たとえ相手方配偶者が離婚に同意しなくても、裁判を通じて離婚が認められる可能性が高まります。
慰謝料請求の根拠と対象者
不貞行為は、配偶者の貞操義務に違反し、夫婦の婚姻共同生活の平穏を侵害する不法行為であるため、これにより精神的苦痛を被った被害者は、その損害に対する賠償として慰謝料を請求することができます。この慰謝料請求の対象は、不貞行為を行った「配偶者」本人と、その「不貞相手」の双方に及びます。これは、不貞行為が夫婦間の義務違反であると同時に、婚姻共同生活の平和を侵害する第三者による不法行為でもあると法的に評価されるためです。
不貞相手に対して慰謝料を請求する場合、不貞相手が、性交渉の相手が既婚者であることを「知っていた」、または「通常知り得る状況にあった」(故意または過失)ことが要件となります。例えば、既婚者であることを隠していたために不貞相手が全く知らなかった場合や、独身であると信じるに足る明確な理由があった場合には、不貞相手に対する慰謝料請求が認められないことがあります。この「故意過失」の要件は、不貞相手の責任を問う上で極めて重要な要素であり、請求側は不貞相手が既婚者であることを認識していた、あるいは認識すべきであった状況を立証する必要があります。
不貞行為の慰謝料
不貞行為によって請求される慰謝料の一般的な相場は、50万円から300万円程度とされています。この金額は、不貞行為によって被害者が被った精神的苦痛の度合いを客観的に評価し、様々な事情を総合的に考慮して算定されます
慰謝料の具体的な金額は、上記の相場を基準としつつも、以下の様々な要素を総合的に考慮して決定されます。
婚姻期間の長さ→婚姻期間が長いほど、夫婦共同生活の平穏が長期間にわたって築かれてきたと評価され、その侵害による精神的苦痛が大きいと判断されるため、慰謝料額は高くなる傾向があります。
子どもの有無と影響→未成熟の子どもがいる場合、不貞行為が子どもに与えた精神的苦痛や、家庭環境への悪影響も考慮され、慰謝料額の増額事由となることがあります。
不貞行為の期間・回数・態様→不貞行為の期間が長期間にわたるほど、回数が多いほど、またその態様が悪質である(例:妊娠・中絶に至った場合、積極的に関係を継続しようとした場合など)ほど、精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料額は高くなります。
精神的苦痛の度合い→不貞行為によって、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症し、通院や治療が必要になった場合など、被害者の精神的苦痛の度合いが重いと判断されれば、慰謝料が増額される可能性があります。
不貞行為後の対応→不貞行為を行った配偶者や不貞相手が、不貞の事実を認め、誠実な謝罪を行い、関係を解消した場合は、慰謝料が減額される要因となることがあります。逆に、不貞を認めず、反省の態度が見られない場合は、慰謝料が増額される可能性があります。
財産分与との関係→財産分与は、離婚に伴う夫婦の共有財産を清算する制度であり、不貞慰謝料とは性質が異なります。そのため、財産分与を受けていたとしても、慰謝料額が当然に減額されるわけではありません。
これらの要因を総合的に評価することで、裁判所は不貞行為によって受けた精神的苦痛を金額で算出し、個別の事案に応じた慰謝料額を決定します。
不貞行為に対する慰謝料請求には、民法によって定められた時効期間が存在します。この期間を過ぎると、原則として慰謝料を請求する権利が失われるため、注意が必要です。
時効期間と起算点
不貞行為に関する慰謝料請求権の消滅時効は、以下のいずれか早い方が到来した時点で完成します。
不法行為および加害者を知ったときから3年間
不貞行為の事実と、その相手(配偶者と不貞相手)を特定できたときから3年以内に権利を行使する必要があります。ここでいう「不貞相手を知ったとき」とは、不貞相手の名前や住所などが特定できている状態を指し、単に顔を知っているだけでは時効期間のカウントは開始されません。
不法行為があったときから20年間
不貞行為の事実や加害者を知らないままであっても、最後に不貞行為が行われたときから20年が経過すると、慰謝料請求権は消滅します。
請求相手によって時効の起算点が異なる場合があります。配偶者に対する不倫慰謝料は不貞の事実を知った日から3年、不倫相手に対する不倫慰謝料は不貞の事実と不倫相手を知った日から3年です。また、不倫が原因で離婚した場合の「離婚慰謝料」は、離婚が成立した日から3年間請求が可能です。
時効の停止・猶予
時効期間が迫っている場合でも、その進行を停止または猶予させる方法が存在します。例えば、内容証明郵便を送付して慰謝料を請求(催告)することで、時効の完成を6ヶ月間猶予させることができます。また、慰謝料について協議を行う旨の合意を当事者間で書面によって行うことで、合意があったときから1年間、または合意で定められた協議期間(1年未満)の間、時効の進行が停止されます。
証拠として使えるもの
不貞行為は秘密裏に行われることが多いため、一つの証拠だけで肉体関係が明確に認められることは稀であり、複数の証拠を組み合わせて総合的に不貞関係の存在を推認させることが重要です。
有効な証拠としては、以下があります。
写真・動画・音声記録→ラブホテルへの出入り、不貞相手の自宅への宿泊、親密な様子の写真や動画、不貞行為を自白している音声記録など。顔や日時がはっきりと特定できるものが有力です。
SNSやLINEなどのメッセージ→肉体関係を匂わせる具体的なやり取りや、不貞行為を認める内容のメッセージ。
探偵(興信所)の調査報告書→ラブホテルへの入室記録など
自白→不貞行為を行った当事者による自白は、最も直接的で強力な証拠となります。
その他→ホテルの領収書、カード明細、交通系ICカードの履歴、カーナビやGPSの記録なども、単体では弱いものの、他の証拠と組み合わせることで不貞行為の存在を推認させる補助的な証拠となり得ます。
証拠収集においては、違法な手段(例:住居侵入、盗聴器の設置、GPSの無断設置など)で得た証拠は、有効性が疑問視されるだけでなく、逆に自身が訴えられたり、刑事罰の対象になったりするリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
まとめ
「不倫」という日常的な言葉が指す範囲は広いものの、法的な責任が問われる「不貞行為」は、民法において「既婚者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と明確に定義されています。この定義は、性交渉に限定されず、性交類似行為も含む広範な「性的関係」を対象とし、たとえ1回の行為であっても成立し得ます。
不貞行為は刑法上の犯罪ではありませんが、民法上の不法行為に該当し、夫婦間の貞操義務違反として、離婚原因や慰謝料請求の根拠となります。慰謝料の相場は、夫婦関係が離婚に至るか否かによって大きく変動し、その具体的な金額は婚姻期間の長さ、子どもの有無、不貞行為の期間や態様、精神的苦痛の度合いなど、多岐にわたる要因を総合的に考慮して決定されます。
また、例外的に性的関係がなくても、不倫相手の行為が婚姻共同生活の平和を積極的に破壊し、夫婦関係の破綻を決定づけたと認められる場合には、不貞行為に準ずる不法行為として慰謝料請求が認められる可能性もあります。
不貞行為に関する慰謝料請求には、原則として不貞の事実と加害者を知ってから3年、または不貞行為があったときから20年という時効期間が設けられています。この期間内に、ラブホテルへの出入りの写真、肉体関係を示唆するメッセージ、自白、探偵の調査報告書など、客観的で有効な証拠を収集することが必要です。
出典(2025年6月24日アクセス)
- 不倫で精神的苦痛を受けた場合の示談金・慰謝料の相場と請求方法, 6月 24, 2025にアクセス、 不倫で精神的苦痛を受けた場合の示談金・慰謝料の相場と請求方法
- 配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか, 6月 24, 2025にアクセス、 配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか
- 慰謝料相場丸ごと解説!浮気や離婚で損しない金額にするための判断軸, 6月 24, 2025にアクセス、 慰謝料相場丸ごと解説!浮気や離婚で損しない金額にするための判断軸
- 1回の不貞行為の慰謝料相場は?判例と合わせて解説, 6月 24, 2025にアクセス、 1回の不貞行為の慰謝料相場は?判例と合わせて解説
- 浮気・不倫の慰謝料請求の時効は何年?時効のパターンや時効を止める方法を解説 – 離婚問題, 6月 24, 2025にアクセス、 浮気・不倫の慰謝料請求の時効は何年?時効のパターンや時効を止める方法を解説
- 不貞行為の証拠収集と立証方法|慰謝料請求・離婚に有利となる記録の集め方, 6月 24, 2025にアクセス、 不貞行為の証拠収集と立証方法|慰謝料請求・離婚に有利となる記録の集め方







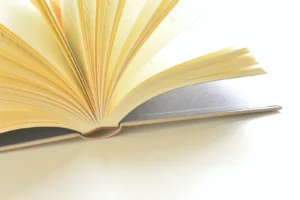
コメント