聴聞制度の意義
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的としています。この法律は、行政法における通則法として、行政活動の基本的なルールを定めるものです。行政活動は国民の生活や経済活動に直接的な影響を与えるため、その過程が適正であることは極めて重要です。
聴聞制度は、行政庁が国民に対して不利益処分を行おうとする際に、その処分を受ける者(名あて人)に意見を述べ、証拠を提出する機会を与えることで、処分の適正性を担保し、国民の権利利益を保護するための重要な手続きとして位置づけられています。
聴聞制度の概要
聴聞の定義と目的
聴聞とは、行政庁が特定の相手方に対し、許認可の取消しや資格の剥奪など、より重大な不利益処分を行おうとする場合に、その名あて人に対し、公開の場で意見を述べ、証拠を提出する機会を与える手続きを指します。
その主要な目的は、予定される不利益処分が、事実と異なる点や不可抗力による原因など、名あて人側の主張によって再考される機会を行政機関に与え、処分の妥当性・慎重性を確保することにあります 例えば、運転免許の取消しや営業許可の取消しといった、個人の社会経済活動に大きな影響を与える処分がその典型です。
聴聞の目的は、不利益処分の「妥当性を再考する手続き」であると明確にされています。これは、聴聞が単に意見を聞く場に留まらず、行政庁が当初の判断を、当事者からの新たな情報や解釈に基づいて再評価する能動的な機会であることを意味します。聴聞は、当事者の視点から事実関係を明らかにし、行政庁がより正確な情報を得て最終判断を下すための、実質的な「処分前再検討」および「事実確認」のプロセスとして機能します。
聴聞が義務付けられる不利益処分とその例外
行政手続法第13条第1項第1号により、聴聞が義務付けられる不利益処分は、その影響が重大なものに限定されています。具体的には、許認可等の取消し、名あて人の資格または地位の剥奪、役員の解任命令・除名命令などが挙げられます。消防法における各種命令(防火対象物の改修命令、使用停止命令、危険物施設の使用停止命令など、緊急の場合を除く)も聴聞の対象となり得ます。
一方で、行政手続法第13条第2項には、意見陳述の手続き(聴聞または弁明の機会の付与)が不要となる例外規定が設けられています。これには、公益上の緊急性があり手続きを執ることができない場合、客観的な資料により資格の不存在または喪失が直接証明された場合、技術的基準の不充足が客観的な方法で確認された場合、金銭の納付命令や給付制限、または課される義務の内容が著しく軽微な処分などが含まれます。
弁明の機会の付与との比較
聴聞と弁明の機会の付与は、いずれも不利益処分に対する意見陳述の機会を行政庁が与える手続きですが、その適用される処分内容と審理方法に明確な違いがあります。
聴聞は「口頭審理」が原則であり、より重大な不利益処分(許認可の取消し、資格剥奪など)に適用されます。これに対し、弁明の機会の付与は原則として「書面審理」であり、聴聞に該当しない比較的軽微な不利益処分に適用されます。
また、弁明の機会の付与では、聴聞で認められる利害関係人の参加、文書の閲覧請求権、調書や報告書の作成・参酌義務といった厳格な手続き上の保障は準用されていません。
| 項目 | 聴聞 | 弁明の機会の付与 |
| 適用される処分内容 | 許認可等の取消し、資格・地位の剥奪など、より重大な不利益処分 | 聴聞に該当しない不利益処分 |
| 審理方法 | 口頭審理が原則 | 書面審理が原則(行政庁が認めた場合に限り口頭弁明可) |
| 利害関係人の参加 | ○ | ✗ |
| 文書閲覧権 | ○ | ✗ |
| 調書・報告書の有無 | 作成義務あり | なし |
| 代理人の選任可否 | ○ | ○ |
| 審査請求の可否 | 最終処分に対しては可 | ○ |
聴聞に関与する主要な関係者とその役割
行政庁
行政庁は、聴聞の実施を決定し、不利益処分を最終的に決定する権限を持つ主体です。聴聞の通知を当事者に行い、主宰者から提出される聴聞調書と報告書の内容を十分に参酌(考慮)して、最終的な処分を決定します。また、聴聞終結後に必要と認められる場合、主宰者に対して聴聞の再開を命じることもできます。
行政庁は最終的な意思決定者であり、主宰者の意見は拘束力を持たないものの、その意見を考慮する義務があります。
主宰者
主宰者は、聴聞の審理を進行する役割を担う者で、行政庁が指名する職員、または政令で定める者が務めます。聴聞の公正性を保つため、当事者や参加人、その配偶者、四親等内の親族、同居の家族、代理人、補佐人など、当事者側の関係者は主宰者になることができません。
主宰者は、聴聞期日に当事者や参加人の意見を聞き、証拠書類等の提出を受け付けます。また、当事者または参加人が行政庁の職員に質問する際には、主宰者の許可が必要です。聴聞終結後には、聴聞の審理経過を記載した調書と、不利益処分に対する当事者等の主張に理由があるかどうかの意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出する義務があります。自身の判断で聴聞を再度行うことを決定することも可能です。
主宰者になれない者の厳格な規定や、「公正を保つ為」という目的の明記は、主宰者が単なる議事進行役ではなく、聴聞手続きの公平性を実質的に担保する重要な役割を担っていることを示しています。彼らが作成する調書(議事録)と、自身の意見を付した報告書は、行政庁が最終決定を下す際の重要な判断材料となり、行政の恣意性をチェックする機能も果たします。
当事者
当事者は、聴聞において、不利益処分を受ける可能性のある直接の対象者です。聴聞期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出する権利を有します。また、期日への出頭に代えて、陳述書および証拠書類等を提出することも可能です。聴聞終結後には、作成された調書および報告書の閲覧を求めることができます。
当事者が意見を口頭で述べたり、書面で提出したり、証拠を提出したりする複数の機会が保障されていることは、聴聞が当事者にとって単なる形式的な場ではなく、「自己弁解・防御」のための実質的な機会であることを示唆しています。行政庁が最終決定において調書や報告書を「十分に参酌」する義務があることを考慮すると、当事者の積極的な参加が、最終的な不利益処分の内容や妥当性に影響を与える可能性を秘めていると言えます。
参加人
参加人は、当事者以外の者で、聴聞の対象となる不利益処分によって自己の利益を害される可能性がある者です。主宰者の職権または主宰者の許可を得て聴聞手続きに参加することができます。参加人も当事者と同様に、意見を述べ、証拠書類等を提出し、調書および報告書の閲覧を求める権利を有します。
代理人
聴聞の通知を受けた当事者または参加人は、代理人を選任することができます。代理人は、当事者または参加人のために、聴聞に関する一切の行為を行うことができ、その資格は書面で証明する必要があります。行政書士が依頼者の代理人として聴聞に出頭し、意見を行政機関に伝えることが実務上行われています。
行政書士のような専門家が代理することで、当事者は法的に適切な主張を展開し、証拠を効果的に提示することができます。これにより、当事者の防御権が実質的に強化され、行政庁との間の情報格差や専門知識の格差が是正され、手続きの公平性がさらに高まる効果が期待されます。
補佐人
通訳などが補佐人に該当し、当事者が主宰者の許可を得て、補佐人とともに聴聞期日に出頭することができます。代理人とは異なり、補佐人の資格証明は不要です。
聴聞制度は複数の関係者が関与し、それぞれに異なる役割と権限が与えられています。
| 関係者 | 定義/役割 | 主な権利/義務 | 関連条文 (行政手続法) |
| 行政庁 | 聴聞の実施を決定し、最終的な不利益処分を決定する権限を持つ機関。 | 聴聞の通知、主宰者の指名、調書・報告書の参酌義務、聴聞の再開命令 | 第13条, 第15条, 第19条, 第25条, 第26条 |
| 主宰者 | 聴聞の審理を進行する者。行政庁が指名する職員または政令で定める者。公正性の確保のため、当事者側の関係者は除外される。 | 審理の進行、意見・証拠提出の受付、質問の許可、調書・報告書の作成・提出、続行期日の指定、聴聞の終結 | 第19条, 第20条, 第21条, 第22条, 第23条, 第24条 |
| 当事者 | 聴聞において不利益処分を受ける可能性のある直接の対象者。 | 意見陳述、証拠書類等の提出、代理人の選任、陳述書等の提出、文書等の閲覧、調書・報告書の閲覧 | 第13条, 第15条, 第16条, 第18条, 第20条, 第21条, 第24条 |
| 参加人 | 当事者以外の者で、不利益処分によって自己の利益を害される可能性がある者。主宰者の許可を得て聴聞に参加。 | 意見陳述、証拠書類等の提出、代理人の選任、陳述書等の提出、文書等の閲覧、調書・報告書の閲覧 | 第17条, 第18条, 第20条, 第21条, 第24条 |
| 代理人 | 当事者または参加人の代理として聴聞に出席する者(例:行政書士)。 | 当事者/参加人のために聴聞に関する一切の行為を行う。資格の書面証明義務。 | 第16条, 第17条 |
| 補佐人 | 当事者または参加人とともに聴聞に出席し、助言等を行う者(例:通訳)。主宰者の許可が必要。 | 当事者/参加人の補佐。資格証明不要。 | 第20条 |
聴聞の具体的な手続の流れ
聴聞手続きは、行政手続法に定められた一連の厳格なステップを経て進行します。各段階における具体的な内容と、関連する法的規定を理解することは、適正な手続きの実施に不可欠です。
聴聞の通知(行政手続法第15条)
行政庁は、聴聞を行うにあたり、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、書面により通知しなければなりません。
通知書には、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日と場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称と所在地といった事項を明記する必要があります。さらに、この書面には、当事者が聴聞期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出できること、または出頭に代えて陳述書等を提出できること、そして聴聞が終結するまでの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができることなどが教示されなければなりません。
名あて人の所在が判明しない場合、行政庁は、その氏名や聴聞に関する事項を事務所の掲示場に掲示することで通知を行うことができ、この場合、掲示を始めた日から2週間を経過したときに通知がその者に到達したものとみなされます。
代理人の選任(行政手続法第16条)
行政庁からの通知を受けた当事者は、代理人を選任する権利を有します。代理人は、当事者のために聴聞に関する一切の行為を行うことができ、その資格は書面で証明する必要があります。
参加人の参加(行政手続法第17条)
聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、聴聞手続きへの参加を求め、または許可することができます。参加人も代理人を選任することができ、その代理人には第16条の規定が準用されます。
文書等の閲覧請求権(行政手続法第18条)
当事者および不利益処分によって自己の利益が害されることとなる参加人(当事者等)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案の調査結果に係る調書や不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、閲覧を拒むことはできません。この権利は、聴聞期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をさらに求めることも妨げません。
文書等の閲覧請求権は、当事者が単に意見を述べるだけでなく、行政庁が処分を決定する根拠となる事実や証拠を事前に確認し、それに基づいて反論を構築するために不可欠です。この権利が実質的に保障されなければ、聴聞は「一方的な説明会」に過ぎず、当事者の「自己弁解・防御」の機会は著しく損なわれます。第三者の利益との調整規定があるものの、この権利は行政の透明性を高め、当事者の実質的な防御権を保障する上で極めて重要です。
聴聞の主宰(行政手続法第19条)
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰します。主宰者は、聴聞の公正性を確保するため、当該聴聞の当事者または参加人、その配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人または補佐人、過去にこれらの者であった者、またはこれらの者の後見人等に該当してはならないとされています。
聴聞期日における審理の方式(行政手続法第20条)
最初の聴聞期日の冒頭では、主宰者は行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容、根拠法令の条項、およびその原因となる事実を、出頭した当事者等に対し説明させなければなりません。
当事者または参加人は、聴聞期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出することができ、主宰者の許可を得て行政庁の職員に質問することも可能です。また、主宰者の許可を得て、補佐人とともに聴聞期日に出頭することもできます。
当事者または参加人の一部が出頭しない場合でも、聴聞期日における審理は行うことができます。
聴聞期日における審理は、行政庁が公開を相当と認める場合を除き、原則として公開されません。
陳述書等の提出(行政手続法第21条)
当事者または参加人は、聴聞期日への出頭に代えて、聴聞期日までに主宰者に対し陳述書および証拠書類等を提出することができます 1。主宰者は、聴聞期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、提出された陳述書および証拠書類等を示すことができます 1。
続行期日の指定(行政手続法第22条)
主宰者は、聴聞期日における審理の結果、聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができます 1。この場合、当事者および参加人に対し、次回の聴聞期日と場所を書面により事前に通知しなければなりませんが、聴聞期日に出頭した者に対しては、当該期日においてこれを告知すれば足ります 1。
聴聞の終結(行政手続法第23条)
主宰者は、当事者の全部または一部が正当な理由なく聴聞期日に出頭せず、かつ陳述書等を提出しない場合、または参加人の全部または一部が聴聞期日に出頭しない場合、改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えることなく聴聞を終結することができます 1。上記以外の場合で、当事者の全部または一部が聴聞期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合において、これらの者の聴聞期日への出頭が相当期間見込めないときは、主宰者は期限を定めて陳述書および証拠書類等の提出を求め、その期限が到来したときに聴聞を終結することができます 1。
聴聞調書及び報告書の作成・提出(行政手続法第24条)
主宰者は、聴聞の審理経過を記載した調書を作成し、その中で不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなりません。
調書は、審理が行われた場合は各期日ごとに、行われなかった場合は聴聞終結後速やかに作成する必要があります。
主宰者は、聴聞終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかの意見を記載した報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければなりません。調書は聴聞審査の議事録、報告書は主宰者の意見を指します。当事者または参加人は、調書および報告書の閲覧を求めることができます。
主宰者が自身の意見を付した報告書を行政庁に提出する義務は、聴聞手続きの核心をなすものです。
この報告書は、聴聞の場で展開された口頭での議論や提出された証拠を、最終的な決定権者である行政庁が理解しやすい形でまとめたものであり、聴聞の成果を決定プロセスに反映させるための不可欠なツールです。これにより、聴聞が単なる形式に終わらず、行政庁の最終判断に実質的な影響を与えることが保証されます。
聴聞の再開(行政手続法第25条)
行政庁は、聴聞終結後に生じた事情を考慮し、必要と認める場合、主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命じることができます。これは、審理後に新たな事実が判明した場合などに、行政庁がより慎重な判断を行うための機会を提供するものです。
不利益処分の決定(行政手続法第26条)
行政庁は、不利益処分の決定をする際、第24条第1項の調書の内容および同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して行わなければなりません。行政庁は主宰者の意見に拘束されるわけではありませんが、調書に記載のない事実に基づいて判断してはならないとされています。
行政庁が主宰者の意見に「拘束されない」とされつつも、「十分に参酌しなければならない」という規定は、単なる形式的な考慮義務以上の意味を持ちます。これは、行政庁が聴聞の過程で明らかになった事実や主宰者の評価を、その判断の根拠として真摯に受け止め、考慮しなければならないという法的義務を課すものです。
| 手続の段階 | 具体的な内容 | 関連条文 (行政手続法) | 主な関係者の役割 |
| 聴聞の通知 | 行政庁が名あて人に対し、予定される処分内容、根拠、原因事実、期日・場所などを書面で通知。閲覧権や意見陳述権を教示。所在不明の場合は掲示。 | 第15条 | 行政庁、名あて人 |
| 代理人の選任 | 通知を受けた当事者・参加人が代理人を選任。代理人は一切の行為が可能。書面による資格証明が必要。 | 第16条 | 当事者、参加人、代理人 |
| 参加人の参加 | 主宰者が利害関係人の参加を求め、または許可。参加人も代理人を選任可能。 | 第17条 | 主宰者、参加人 |
| 文書等の閲覧請求権 | 当事者・参加人が、聴聞通知から終結まで、処分原因事実を証する資料の閲覧を請求可能。行政庁は正当な理由なく拒否不可。 | 第18条 | 当事者、参加人、行政庁 |
| 聴聞の主宰 | 行政庁が指名する職員等が主宰。公正性確保のため、当事者等の関係者は主宰者になれない。 | 第19条 | 行政庁、主宰者 |
| 聴聞期日における審理の方式 | 主宰者が行政庁職員に処分内容等を説明させ、当事者等が意見陳述、証拠提出、質問(主宰者の許可要)、補佐人同伴(主宰者の許可要)が可能。審理は原則非公開。 | 第20条 | 主宰者、行政庁職員、当事者、参加人、補佐人 |
| 陳述書等の提出 | 当事者・参加人が期日への出頭に代えて、主宰者に陳述書や証拠書類等を提出可能。 | 第21条 | 当事者、参加人、主宰者 |
| 続行期日の指定 | 主宰者が審理の結果、続行が必要と認めれば新たな期日を指定。書面で通知(出頭者には口頭告知可)。 | 第22条 | 主宰者、当事者、参加人 |
| 聴聞の終結 | 当事者等が正当な理由なく不出頭・不提出の場合、主宰者は意見陳述機会を与えずに終結可能。 | 第23条 | 主宰者、当事者、参加人 |
| 聴聞調書及び報告書の作成・提出 | 主宰者が審理経過の調書と、当事者等の主張に対する意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出。当事者等は閲覧可能。 | 第24条 | 主宰者、行政庁、当事者、参加人 |
| 聴聞の再開 | 行政庁が聴聞終結後の事情を考慮し、必要と認めれば主宰者に報告書を返戻し、聴聞の再開を命令。 | 第25条 | 行政庁、主宰者 |
| 不利益処分の決定 | 行政庁は、調書の内容と報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して不利益処分を決定。調書にない事実に基づく判断は不可。 | 第26条 | 行政庁 |
聴聞手続の瑕疵と処分の違法性
聴聞手続きに瑕疵があった場合、それが直ちに処分の違法性につながるかについては、判例で様々な判断が示されています。
主要な判例を以下に示します。
| 判例名 | 判決年月日 | 事案の概要 | 判旨(手続き上の瑕疵と処分の違法性の関係) | 実務上の示唆 |
| 群馬中央バス事件 | 最一小判昭50.5.29 | 運輸審議会の公聴会で、申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかった手続き上の瑕疵があった。 | 仮に機会を与えたとしても、申請者が判断を左右する資料を提出しうる可能性がなかった場合、処分は直ちに違法とはならない。 | 手続き上の瑕疵があっても、それが処分の結論に実質的な影響を与えないと判断される場合は、直ちに処分が違法となるわけではない。ただし、これは例外的な判断であり、原則として適正な手続きの履行が求められる。 |
| 個人タクシー事件 | 最判昭46・10・28 | 個人タクシー事業申請が、内部基準不適合で却下。聴聞担当官が基準を知らず、申請者に確認を怠った。 | 審査基準の不周知や、聴聞で主張・証拠提出の機会を十分に与えなかった審査手続は瑕疵であり、却下処分は違法。 | 聴聞は実質的な防御の機会として機能しなければならず、審査基準に関する情報提供や主張・立証の機会が保障されなければ手続きの適正性が損なわれる。 |
| 一級建築士免許取消処分等取消請求事件 | 最三小判平成23年6月7日 | 一級建築士の免許取消処分で、通知書に処分基準の適用関係が全く示されていなかった。 | 処分基準の適用関係が示されなければ、名宛人が処分理由を了知できず、理由提示として不十分であり、処分は違法。 | 単に違反事実と根拠法令を示すだけでなく、「処分基準の適用関係」まで具体的に記載することが、適正な理由提示の必要条件である。理由提示は、行政庁の判断の慎重・合理性を担保し、相手方に不服申立ての便宜を与え、説得機能を果たすために重要。 |
| 聴聞主宰者の適格性に関する判例(裁判例6) | 東京高判平成21年10月14日 | 不利益処分に密接に関わった公務員が聴聞主宰者となった事案。 | 行政手続法19条2項は明示的に除斥しておらず、他の制度で手続的公正さが担保されているため、法の趣旨を没却するような重大な違法とはいえない。 | 主宰者の選任において、形式的な適格性だけでなく、実質的な公正性が他の手続きで担保されているかどうかが判断のポイントとなる。 |
| 文書閲覧拒否に関する判例(裁判例4, 5) | 東京高判平成21年10月14日 | 聴聞に先立つ書類の閲覧請求が一部拒否された事案。 | 閲覧拒否が防御権の行使を実質的に妨げない場合や、弁明内容・行政庁の認定判断に重大な影響を及ぼさない場合は、取消事由にはならない。 | 文書閲覧権は重要だが、その侵害が直ちに処分の違法性につながるわけではなく、防御権の実質的な阻害があったかどうかが問われる。 |
聴聞と行政不服審査請求の関係(行政手続法第27条)
行政手続法第27条により、聴聞の規定に基づく処分またはその不作為については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができません。
この規定は、聴聞手続きそのものの中で行われた行政庁の対応(例:文書閲覧の不許可処分、利害関係人の参加不許可処分など)に対して、個別に審査請求を行うことを制限するものです。聴聞という手続き自体が、不利益処分に対する国民の意見陳述の機会を保障するものであるため、その手続き内部の個別の行為を繰り返し審査請求の対象とすることは、行政の円滑な運営を阻害するとの趣旨が背景にあります。最終的な不利益処分自体は、行政不服審査請求の対象となります。
聴聞中の手続きに関する審査請求が制限されているのは、手続きの無限連鎖を防ぎ、行政プロセスの効率性を確保するためです。聴聞は、それ自体が不利益処分に対する包括的な意見陳述の機会として設計されています。
もし聴聞中のあらゆる個別の決定(例:文書閲覧の可否)に対して個別に不服申立てが認められれば、行政手続きは停滞し、迅速な行政活動が困難になります。この規定は、最終的な不利益処分に対しては不服申立てを認める一方で、その前段階の手続き内部の行為については、最終処分に対する不服申立ての際にまとめて主張すべきであるという考え方に基づいています。
結論
行政手続法における聴聞制度は、行政の公正性・透明性を確保し、国民の権利利益を保護するための不可欠な手続きです。
引用文献
- 市町村アカデミー 講義 – 行政手続法の要点
- 行政手続の意義
- 富山綜合法務事務所 聴聞手続きとは
- 行政書士 樋口法務事務所 聴聞代理
- 行政手続制度について 政策法務ニュースレター
- 豊明市 行政手続法Q&A
- 総務省|行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)|行政手続法Q&A
- 行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続(意見陳述=聴聞・弁明の機会の付与)
- 法務特別セミナー R3/11/2(埼玉県) 板垣 勝彦(横浜国立大学)
- 行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
- 行政手続法に出てくる「聴聞」と「弁明の機会の付与」とは?2つの用語の違いについて解説します!
- 行政手続法15条:聴聞の通知の方式
- 新銀座法律事務所 行政処分対象事案報告書の提出を求める書面が送られてきました
- 行政手続法 | e-Gov 法令検索
- 不利益処分に係る聴聞と理由提示
- 行政手続法26条:聴聞を経てされる不利益処分の決定
- 行政手続法上の瑕疵と処分の違法性判断のための一考察 ─ 聴聞と弁明の機会の付与を中心
- PowerPoint プレゼンテーション http://www.rilg.or.jp/htdocs/uploads/r4_tokubetu_saitama_03.pdf
- 行政手続法27条:審査請求の制限

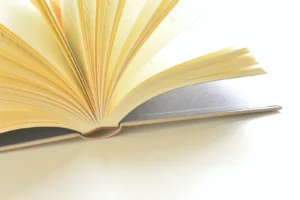

コメント