行政指導の定義
行政手続法第2条第6号において、行政指導は「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義されている。
この定義からは、行政指導の主要な4つの要素が導き出される。
- 組織法上の根拠があること: 行政機関がその任務または所掌事務の範囲内で行うこと。
- 一定の行政目的の実現を目指すものであること: 特定の行政目的を達成するために行われること。
- 特定人に向けられたものであること: 特定の個人や事業者に対して行われること。
- 相手方の任意を前提とすること: 相手方の自主的な協力によってのみ実現される行為であり、法的拘束力を持たないこと。
例えば、役所が事業者に対して営業内容の改善を求める行為などが、この行政指導に該当する。
定義の中に「任務又は所掌事務の範囲内」と「相手方の任意を前提」という規範的な要素が含まれていることは、行政指導の濫用を未然に防ぐための、法的拘束力を持たない行政活動に対する根本的な制約として機能している。
行政手続法の目的が「公正の確保と透明性の向上」であることから、行政指導がその性質上、濫用されやすい側面を持つため、定義段階でその限界と本質的な性格を明示することで、行政機関が行政指導を行う際の基本的な指針を与えている。
特に「任意性」は、行政指導と行政処分を分かつ最も重要な要素であり、これが定義に明記されることで、後述する不利益取扱いの禁止(第32条第2項)や権限行使示唆の禁止(第34条)といった濫用防止規定の根拠となっている。
このように、行政指導の定義は単なる説明ではなく、行政指導が適法かつ適正に行われるための「最低限の要件」を提示しており、行政指導が行政機関の恣意的な権力行使の道具となることを防ぎ、国民の権利利益を保護する第一歩となっている。
行政指導と行政処分の本質的な違い
行政指導と行政処分は、行政活動の二つの主要な形態であるが、その法的性質において本質的な違いがある。
行政指導は、相手方に法律上の義務を課したり、権利を制限したりする「法的拘束力」を持たない。あくまで相手方の自主的な協力を前提とした「お願い」や「助言」の性質を持つため、行政指導を受けた者がこれに必ず従う義務はない。
一方、行政処分は、法律に基づいて個人の権利を制限したり義務を課したりする強制力を持つ行為である。例えば、営業許可の取消しや営業停止命令などがこれに該当する。
行政指導は、しばしば行政処分(レッドカード)の一歩手前、あるいは法令違反のグレーゾーンにおいて、行政目的達成のために発せられる「イエローカード」のような位置づけにある。
行政処分に対しては、行政不服審査法に基づく「不服申立て」や行政事件訴訟法に基づく「抗告訴訟」といった法的救済手段が認められるが、行政指導は原則として抗告訴訟の対象とはならない。
行政指導の「法的拘束力がない」という原則は、国民の自由を保障する上で極めて重要である。しかし、行政機関の優越的な地位や、行政指導がしばしば行政処分に先行するという実態は、国民にとって事実上の強制力を生み出す可能性がある。行政指導は、行政機関が持つ情報力、専門性、そして許認可権限や処分権限といった「潜在的な権力」を背景に行われるため、たとえ法的拘束力がなくても、国民や事業者は「従わなければ不利益を被るかもしれない」という心理的な圧力を感じやすい。特に、行政指導が「警告」として発せられたり、行政処分の一歩手前と位置づけられたりする
場合、その事実上の影響力は無視できない。この「法的拘束力の欠如」と「事実上の強制力」との間の緊張関係こそが、行政手続法が行政指導を厳しく規律する主要な理由であり、行政指導の適正化を巡る法的議論の核心をなしている。
行政手続法は、行政指導の「任意性」という建前を維持しつつ、その実態としての「事実上の強制力」を抑制するための具体的なルールを設けることで、行政の柔軟な対応と国民の権利保護という二律反的な目的の調和を図っている。この緊張関係を理解することが、行政指導の法的性質を深く理解する鍵となる。
以下の表は、行政指導と行政処分の主要な違いをまとめたものである。
表1:行政指導と行政処分の比較
| 項目 | 行政指導 | 行政処分 |
| 法的拘束力 | なし(相手方の任意的協力に依拠) | あり(法律に基づき強制力を持つ) |
| 根拠 | 原則不要(ただし、濫用防止規定はあり) | 必要(法律の根拠に基づく) |
| 相手方の義務 | なし(従う義務はない) | あり(従う義務が生じる) |
| 従わない場合の効果 | 原則として不利益な取扱いは禁止される | 義務違反として法的制裁の対象となり得る |
| 不服申立ての可否 | 原則不可(処分ではないため) | 可能(行政不服審査法、行政事件訴訟法に基づく) |
| 主な法的救済手段 | 行政指導の中止等の求め(第36条の2) | 不服申立て、抗告訴訟 |
| 目的 | 行政目的の実現(非強制) | 法令に基づき、国民の権利義務に直接影響を与える |
| 具体例 | 営業内容の改善勧告、残業代是正勧告 | 営業許可の取消し、営業停止命令、免許剥奪 |
2. 行政指導の一般原則(第32条)
行政手続法第4章「行政指導」は、第32条から第36条の2までで構成されている。第32条は、行政指導の適正な運用を担保するための最も基本的な原則を定めている。
表2:行政手続法 第4章 各条文の概要
| 条文番号 | 条文名 | 主要な内容 | 趣旨/目的 |
| 第32条 | 行政指導の一般原則 | 任務・所掌事務の範囲内、任意性、不利益取扱いの禁止 | 濫用防止、国民の権利保護 |
| 第33条 | 申請に関連する行政指導 | 申請者の権利行使妨害の禁止 | 申請権の保護、手続の公正確保 |
| 第34条 | 許認可等の権限に関連する行政指導 | 権限行使示唆による強制の禁止 | 事実上の強制力排除、任意性の確保 |
| 第35条 | 行政指導の方式 | 趣旨・内容・責任者の明確化、書面交付の原則と例外 | 透明性確保、責任の明確化 |
| 第36条 | 複数の者を対象とする行政指導 | 行政指導指針の策定・公表 | 公平性・予測可能性の確保、行政の裁量規律 |
| 第36条の2 | 行政指導の中止等の求め | 不適法な行政指導に対する申出制度 | 国民の救済、行政の自己是正促進 |
任務・所掌事務の範囲内であることの重要性
行政手続法第32条第1項前段は、行政指導に携わる者が「いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと」を規定している。これは、各行政機関に法律で権限が配分されており、行政指導もその範囲内でしか行えないという「法律による行政の原理」を非権力的な行政活動にも及ぼす趣旨である。
したがって、任務外・所掌事務外の内容について行政指導を行うことは許されない。例えば、食品衛生を所掌する部署が建築基準法上の問題について行政指導を行うことは、その任務の範囲外であり、許されない。
この「任務・所掌事務の範囲内」という原則は、行政指導の「任意性」と並び、行政権の濫用を防止するための基本的な制約である。
この原則がなければ、行政機関は自己の専門外の事項や権限外の事項にまで事実上の影響力を及ぼし、行政の予測可能性と国民の自由を不当に侵害する可能性が生じる。行政機関は、それぞれ特定の行政目的を達成するために設立され、法律によってその権限と任務が定められている。
もし、行政指導がこの範囲を超えて行われることを許せば、例えば食品衛生を管轄する部署が建築基準について指導したり、教育委員会が経済活動について指導したりといった事態が生じうる。
これは、行政の専門性と効率性を損なうだけでなく、国民がどの行政機関からどのような指導を受けるか予測できなくなり、行政の恣意性を招く。この原則は、行政指導が「権限の濫用」とならないための基本的な歯止めであり、行政機関の活動をその本来の目的に限定することで、行政の適正な運営と国民の権利利益の保護を両立させるための重要な規範である。
相手方の任意の協力によることの徹底
行政手続法第32条第1項後段は、行政指導の内容が「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであること」に留意しなければならないと定めている。行政指導は、行政庁が国民に「お願い」をする非権力的な行為であり、行政指導を受けた者はそれに従う法的義務を負わない。
「任意の協力」という原則は行政指導の法的性質を決定づける核心であるが、現実には行政機関の優越的地位により、国民が「拒否する自由」を事実上行使しにくい状況が生じうる。
行政指導は、その柔軟性や迅速性から行政実務で広く用いられてきたが、その過程で、行政機関がその優越的な地位を利用し、事実上相手方に強制するような運用がなされる事例が少なくなかった。
例えば、許認可権限を持つ行政機関が、許認可をちらつかせて行政指導に従わせるといったケースである。
第32条第1項は、このような行政指導の「実態」を認識した上で、行政機関に対し、行政指導はあくまで「お願い」であり、強制ではないことを常に意識するよう求める立法者のメッセージである。
この原則は、行政指導が法的拘束力を持たないという建前を維持しつつ、その実態としての「事実上の強制力」を抑制するための、行政機関に対する倫理的・規範的な指針であり、行政指導が国民の自由な意思決定を尊重する形で運用されることを促している。
行政指導に従わないことを理由とする不利益取扱いの禁止
行政手続法第32条第2項は、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と明確に規定している 3。この規定は、行政指導の任意性を担保するための最も重要な条文であり、行政指導に従わないこと自体を理由とした営業停止や許認可の不許可といった処分は許されない 6。
ただし、行政指導に従わなかった結果、法令違反の事実が発覚し、その法令違反自体を理由として処分がなされる場合は適法である。行政指導に従わないことと、法令違反の事実に対する処分とは明確に区別される 6。
「氏名の公表」については、行政指導の一環として行われる場合、直ちに「不利益な取扱い」に該当するか否かは、その目的、態様、影響などを総合的に判断する必要がある。例えば、パチンコ店が営業自粛要請(行政指導)に従わなかった場合の店名公表は、不利益処分ではなく、行政指導の規定内の行為と解された事例もある 6。
不利益取扱いの禁止は、行政指導の任意性を実効的に保障する核心的規定である。しかし、「不利益な取扱い」の範囲、特に「氏名等の公表」がこれに該当するか否かの判断は、行政指導の事実上の強制力を巡る法的・実務上の課題であり続けている。行政手続法は、直接的な法的拘束力を持たない行政指導の「事実上の強制力」を抑制しようとしているが、公表のような間接的な強制手段に対する明確な基準は必ずしも確立されていない。このグレーゾーンの存在は、行政機関が法的拘束力のない手段で国民を間接的に強制しうる余地を残しており、今後の判例や運用の蓄積がその限界をより明確にする必要がある。第32条第2項は、行政指導の濫用を防止する強力な規定だが、その運用においては、「不利益な取扱い」の解釈が常に問われる。特に、情報公開が進む現代において、公表という手段が行政指導の任意性をどこまで損なうのかは、行政の透明性と国民の権利保護のバランスを考える上で重要な論点である。
3. 特定の状況下における行政指導の規律
申請に関連する行政指導(第33条)
行政手続法第33条は、「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない」と規定している。
これは、行政機関が許認可等の申請を受けた際に、申請を拒否する正式な処分を避けるため、あるいは審査の手間を省くために、申請者に対して申請の取下げや内容変更を不当に求める行政指導が行われることを防止する規定である。
この規定は、行政機関が「行政指導」という非公式な手段を用いて、国民の「申請権」という重要な権利の行使を事実上妨害することを防ぐための、具体的な濫用防止規定である。
行政指導によって申請権の行使が妨げられることは、国民の権利保護の観点から看過できない。
この条文は、行政指導の任意性を申請手続の文脈で特に強調し、行政機関がその優越的地位を利用して、国民の権利行使を事実上阻害することを防ぐ役割を果たす。これは、行政手続法が、行政の透明性と公正性を、形式的な法行為だけでなく、その前段階の非公式な接触においても確保しようとする姿勢を示している。
許認可等の権限に関連する行政指導(第34条)
行政手続法第34条は、「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない」と規定している。
これは、行政機関が許認可等の権限を背景に、その権限を行使する意図がないにもかかわらず、あたかも権限を行使するかのように示唆することで、相手方に行政指導に従うことを事実上強制する行為を禁止するものである。
第34条は、行政指導の「任意性」が、行政機関の持つ「潜在的な権力」によっていかに容易に損なわれうるかという現実を直視した規定である。
行政指導自体は任意だが、行政機関が持つ許認可権限や処分権限が背景にあると、国民は「従わなければ不利益な処分を受けるかもしれない」という心理的な圧力を感じやすい。
行政機関がこの心理を利用し、権限を行使する意図がないにもかかわらず、その可能性を匂わせることで、事実上の強制力を発揮するケースがあった。この条文は、行政機関がその権限を「ちらつかせる」ことによる心理的圧力を明確に禁止することで、行政指導の法的性質である「任意性」を実質的に保障しようとする、行政手続法の強い意思を示している。
これは、行政の「ソフト・ロー」としての行政指導が、ハード・ロー(処分)の代替手段として悪用されることを防ぐための重要な防波堤であり、行政指導が国民の自由な意思決定を尊重する形で運用されることを促し、行政の公正性と透明性を高めることに寄与している。
行政指導の方式(第35条)書面交付の原則と例外
行政手続法第35条は、行政指導に携わる者が、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないと定めている。特に、許認可等の権限を行使し得る旨を示す場合は、その権限を行使できる根拠となる法令の条項、要件、及び権限の行使がその要件に適合する理由を具体的に示す義務がある。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の内容を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、原則として書面を交付しなければならない。
ただし、以下の場合は書面交付が不要となる例外が認められている。
- 行政上特別の支障がある場合。
- 相手方に対しその場において完了する行為を求める場合(例:火災時に避難を口頭で勧告する時)。
- 既に文書又は電磁的記録(メールなど)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める場合。
行政指導の「方式」に関する規定は、行政指導の透明性と明確性を確保し、国民が行政指導の内容を正確に理解し、必要に応じて対応するための基盤を提供する。口頭での曖昧な行政指導は、国民がその内容を正確に把握できない、行政側が後から指導内容を否認・変更する、といった問題を引き起こし、国民の権利保護を困難にする。明確化の原則は、行政指導が「お願い」であるとはいえ、その内容が不明確であれば国民は適切に対応できないため、行政機関に説明責任を課している。書面交付義務は、この明確化を物理的な記録として残すことで、行政指導の透明性を飛躍的に向上させる。これにより、国民は行政指導の適否を判断しやすくなり、不適切な指導に対する「中止等の求め」(第36条の2)などの法的手段を行使する際の証拠となる。方式に関する規定は、行政指導の「任意性」と「濫用防止」を実質的に支えるための、具体的な手続き的保障であり、行政指導がより責任ある、透明性の高い形で運用されることが期待される。
表3:行政指導の書面交付の原則と例外
| 区分 | 内容 |
| 原則(書面交付が必要な場合) | 相手方から行政指導の内容を記載した書面の交付を求められたとき。 |
| 例外(書面交付が不要な場合) | 1. 行政上特別の支障がある場合。 2. 相手方に対しその場において完了する行為を求める場合(例:火災時の避難勧告)。 3. 既に文書又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める場合。 |
4. 複数の者を対象とする行政指導(第36条)
行政指導指針の策定と公表の意義
行政手続法第36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない」と規定している 1。行政指導指針とは、複数の者に対して行われる行政指導に共通してその内容となるべき事項を定めたものである。
この規定により、例えば、特定の業界全体に対する指導や、特定の地域における住民全体への指導など、画一的・反復的に行われる行政指導について、その内容や基準が明確化され、透明性が確保される。複数の者を対象とする行政指導における「行政指導指針の策定と公表」義務は、個別の行政指導の「任意性」を担保するだけでなく、行政指導全体の「公平性」と「予測可能性」を確保するための重要な仕組みである。同じような状況にある複数の事業者や国民に対して、行政機関が異なる内容の指導を行ったり、その基準が不明確であったりすると、不公平感が生じ、行政に対する信頼が損なわれる。指針の策定と公表は、行政機関内部における行政指導の基準を明確にし、担当者による恣意的な運用を防ぐ効果がある。また、国民や事業者は、事前に指針を知ることで、どのような行政指導が行われるか予測できるようになり、自らの行動計画を立てやすくなる。これは、行政の透明性向上と国民の権利利益保護に資するだけでなく、行政指導の「ソフト・ロー」としての役割を強化する。つまり、法的拘束力はないものの、公表された指針は行政機関自身の行動を規律する規範となる。行政指導指針の策定・公表義務は、行政指導が個別の「お願い」に留まらず、一定の行政目的を達成するための「政策手段」として機能する際に、その運用が公正かつ透明であることを担保するための、極めて重要な制度的保障である。
5. 行政指導の適正化と濫用防止の仕組み
行政指導の中止等の求め(第36条の2)
行政手続法第36条の2は、行政指導の相手方が、当該行政指導がその根拠とする法律の要件に適合しないと思料するときは、当該行政機関に対し、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる制度を定めている。
この申出は、申出をする者の氏名・名称・住所、行政指導の内容、根拠法令の条項、要件、適合しない理由、その他参考事項を記載した申出書を提出して行われる 16。申出を受けた行政機関は、必要な調査を行い、行政指導が法律の要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。これは、行政機関が自らの行政指導の適法性を再検討し、是正する義務を負うことを意味する。
ただし、当該行政指導が、その相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものである場合は、行政指導の中止等を求めることはできない。これは、既に相手方の言い分を聞いた上で行政指導がなされているためである。
「行政指導の中止等の求め」は、行政指導が「処分」ではないため抗告訴訟の対象とならないという法的救済の空白を埋める、重要な「準司法的」な仕組みである。行政指導は原則として抗告訴訟の対象外であるにもかかわらず、不適切な行政指導は国民に不利益を与える可能性がある。
この制度は、国民が不適切な行政指導を受けた際に、法的拘束力がないことを理由に放置されるか、あるいは高コストな国家賠償請求訴訟に頼るしかないという救済の不十分さを解消する。行政機関自身に、自らの行政指導の適法性を再検討し、不適法であれば是正する義務を課すことで、行政内部でのチェック機能を強化している。これは、行政機関が「指導」という名の下に不当な行為を行うことを抑制し、国民の権利保護を強化する。
特に、行政機関が「必要な調査を行い、…適合しないと認めるときは、…措置をとらなければならない」という義務規定は、単なる行政機関への「お願い」ではなく、法的義務を課している点で重要である。この制度は、行政指導の柔軟性を維持しつつも、その濫用を効果的に抑制するための、行政手続法における画期的な制度設計であり、行政指導の「任意性」が単なる建前ではなく、実質的に機能するよう担保されている。
処分等の求め(第36条の3)
行政手続法第36条の3は、「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる」と規定してい。
この制度は、法令違反を発見した第三者(利害関係人以外の者でも可)が、行政庁に対して、その是正のための処分や行政指導を行うよう求めることができるものである。ただし、行政指導を求める場合、その根拠となる規定が法律に置かれているものに限られ、条例や規則に根拠規定がある場合は、この制度を利用して行政指導を求めることはできない。申出書には、申出をする者の氏名・名称・住所、法令に違反する事実の内容、求める処分・行政指導の内容、その根拠法令の条項、理由、その他参考事項を記載する必要がある。
「処分等の求め」は、行政機関の「不作為」(なすべき行為をしないこと)に対する国民からの能動的な関与を可能にする、ボトムアップ型の行政監視メカニズムである。行政機関が法令違反を認識しているにもかかわらず、何らかの理由で是正措置を講じない場合、国民はそれを是正する手段が限られていた。この制度は、国民が行政の「番人」として機能することを可能にし、行政機関の職務怠慢を是正するきっかけを提供する。特に、利害関係人以外でも申出ができる点は、公益の保護という観点から重要である。ただし、行政指導を求める場合に「法律に根拠規定があるものに限る」という制約は、行政機関に新たな行動を強制する性質を持つため、その根拠をより厳格に求めていることを示唆している。これは、行政の透明性と公正性を、行政機関の「行為」だけでなく「不行為」の側面からも確保しようとする、行政手続法の包括的なアプローチを示している。
行政指導の限界と判例の動向
行政指導は法的拘束力を持たないため、原則として、その実施には法律の根拠は不要とされている 7。しかし、行政指導が実質的に相手方の任意性を損ない、事実上の強制力を有するに至った場合、その適法性が問題となる。判例は、行政指導が強制にわたるなど、事業主の任意性を損なうことのない限り適法としている 23。
特に、行政指導の「客観的な態様」や「運用の実態」が、相手方の任意性を損なうものであれば、違法と判断されることがある。例えば、寄付金納付を事実上強制しようとした事例で違法とされた判例がある 23。
また、ごく例外的に、行政指導が実質的に処分と評価され、抗告訴訟の対象となると判断された判例(「病院開設中止勧告事件」など)も存在する。これは、行政指導が相手方の権利義務に直接影響を与えるような、極めて強い効果を持つ場合に限られる。
行政手続法が行政指導の任意性を強調する一方で、判例は、行政指導が持つ「事実上の強制力」を厳しく監視し、その限界を画定している。
法的拘束力がないはずの行政指導が、なぜ裁判で争われ、違法と判断されることがあるのかという問いに対し、判例は、行政機関が「お願い」という形式をとりつつも、その背景にある権力や運用の実態によって、国民の自由な意思決定を不当に制限した場合に、その行政指導を違法と判断することで、行政手続法の精神を実質的に担保している。
特に「病院開設中止勧告事件」は、行政指導が事実上処分と同視されるほどの効果を持つ場合に、例外的に抗告訴訟の対象となりうることを示した点で画期的である。
これは、法律の文言だけでは捉えきれない行政実務の複雑性を司法が補完し、行政の「ソフト・ロー」が「ハード・ロー」の原則を潜脱することを防ぐ、重要な「司法審査の役割」を示している。
6. 行政指導の具体例と留意点
様々な行政指導の類型と実際の事例
行政指導は、その機能に着目すると、主に以下の3つに分類できる。
- 規制的行政指導: 相手方の活動を規制することを目的として行われる行政指導であり、相手方にとって不利益に作用するため、法律による行政の原理に照らして最も問題が生じやすい類型とされる。
- 例:残業代の未払いがある事業者に対して、労働基準監督官が是正勧告を行った事例。飲食店が衛生上良くない食品管理をしていた場合に、保健所が立ち入り調査を行い指導・勧告をする事例。倫理的に問題がある表現を放送した放送事業者に対し、総務省が見直しを行うよう求めた事例。
- 助成的行政指導: 相手方に対して情報を提供し、もって私人の活動を助成しようとするものであり、相手方にとって利益的な意味合いを有する。
- 調整的行政指導: 私人間(私人同士)の紛争に行政が介入することで、その解決を図るために行われる形態。
その他の具体例としては、以下のようなものが挙げられる。
- 倒壊しそうで危険な建物について、知事が所有者に対し必要な措置をとることを勧告する事例。
- 許認可の申請要件を一部満たしていなかった事業者に対し、申請を却下する前に、業務体制のさらなる整備を行うよう指導した事例。
- パチンコ店が営業自粛要請(行政指導)に従わなかった際に、行政が店名を公表した事例。これは不利益処分ではなく、行政指導の規定内の行為と解された。
- 大手携帯会社の端末代が「実質0円」になっている仕組みを問題視し、行政が「口頭注意」した事例。
行政指導指針の具体例としては、食品衛生に関する営業許可の基準や、特定の食品の調理・販売に関する衛生管理基準など、複数の事業者に共通して適用される指導内容が指針として定められることがある。
行政指導の類型と具体例の多様性は、行政が社会の複雑な問題に対し、法的強制力に依らない柔軟な対応を可能にするツールとして、行政指導をいかに広く活用しているかを示している。この柔軟性は、行政の効率性を高める一方で、その濫用の可能性を常に内包しており、行政手続法による規律の必要性を裏付けている。行政手続法第4章の規定は、この行政指導の「柔軟性」と「濫用可能性」という二面性を認識した上で、その適正な運用を確保するための共通のルールを設けている。多様な行政指導の形態に対応できるよう、包括的な原則と具体的な濫用防止規定が不可欠であることが示唆される。
国民・事業者が行政指導を受ける際の法的対応と心構え
行政手続法第4章の規定は、単なる行政機関への規範だけでなく、国民・事業者が行政との関係において自らの権利を保護し、主体的に行動するための「行動規範」としての側面を持つ。行政指導を受けた際には、以下の点に留意し、適切に対応することが重要である。
- 行政指導の任意性を理解する: 行政指導は、あくまで行政機関からの「お願い」であり、法的拘束力はないため、必ずしも従う義務はないことを認識すべきである。
- 不利益取扱いの禁止を認識する: 行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な行政処分を受けることはない。この原則を理解し、不当な圧力を受けた場合は、その旨を主張することが重要である。
- 明確化と書面交付を求める: 行政指導の内容が不明確な場合や、口頭での指導を受けた場合は、行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示してもらうよう求めるべきである。特に、口頭指導の場合は、行政指導の内容を記載した書面の交付を要求できることを知っておくことが、後のトラブル回避や証拠保全のために有効である。
- 権限行使示唆への対応: 許認可等の権限を持つ行政機関から、その権限行使を示唆するような行政指導を受けた場合は、行政手続法第34条の規定に基づき、その権限行使の根拠となる法令の条項、要件、理由の提示を求めることができる。
- 不適切な行政指導への対応: 行政指導が、その根拠とする法律の要件に適合しないと思料される場合は、「行政指導の中止等の求め」(行政手続法第36条の2)の制度を活用することを検討すべきである。これにより、裁判所を介さずに、行政機関に直接是正を求めることが可能となる。
- 法令違反の是正を求める: 法令に違反する事実があるにもかかわらず、行政機関が是正のための処分や行政指導を行わない場合は、「処分等の求め」(行政手続法第36条の3)の制度を活用し、行政機関に是正措置を求めることができる。
これらの制度を理解し、適切に活用することが、行政指導の適正な運用を実質的に担保し、行政と国民の間の健全な関係を築く上で不可欠である。行政手続法第4章は、行政指導の適正化を図るだけでなく、国民が行政との関係において「受動的な対象」から「能動的な主体」へと変化するための法的基盤を提供している。これらの制度を国民が積極的に活用することが、法律の目的である「国民の権利利益の保護」を実質的に実現する鍵となる。
7. まとめ
行政指導は、その柔軟性と非強制性ゆえに現代行政において多用される重要な手段である。しかし、国民・事業者は、行政指導の法的性質を正しく理解し、行政手続法第4章に定められたこれらの原則と権利行使の仕組みを適切に活用することで、自らの権利利益を守り、行政の透明性と公正性を高めることに貢献することが可能である。
引用文献(2025年6月10日にアクセス)
- 総務省|行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)|行政手続法Q&A
- 行政手続(処分、行政指導及び届出に関する手続)の概要
- 第10章 行政指導
- 行政手続法32条:行政指導の一般原則
- 今さら聞けない「行政指導」と「行政処分」の違い
- 【事例で簡単に解説】行政指導とは【従わない場合の規定も】
- 行政指導
- 行政手続法第32条 – Wikibooks
- 行政手続法第33条 – Wikibooks
- 行政手続法33条:申請に関連する行政指導
- 行政手続法34条:許認可等に関する行政指導
- 行政手続法第34条 – Wikibooks
- 行政手続法35条:行政指導の方式
- 行政手続法とは?弁護士が概要をわかりやすく解説 | Authense法律事務所
- 行政手続法|条文|法令リード
- 行政手続法第36条の2 – Wikibooks
- 行政手続法36条の2:行政指導の中止等の求め
- 行政手続法36条の3:処分等の求め
- ある法令違反の事実を発見したけれど、行政庁が動いていない・・・そんなときには!【行政手続法 “処分等の求め”とは】 | 行政書士むつろ事務所
- 行政指導, 6月 11, 2025にアクセス、 http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/date9/2017a18.htm
- 行政指導とは?行政処分との違い・従わない場合・具体例・行政手続法のルール・受けた場合の対処法などを分かりやすく解説!
- 横浜市, 食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針
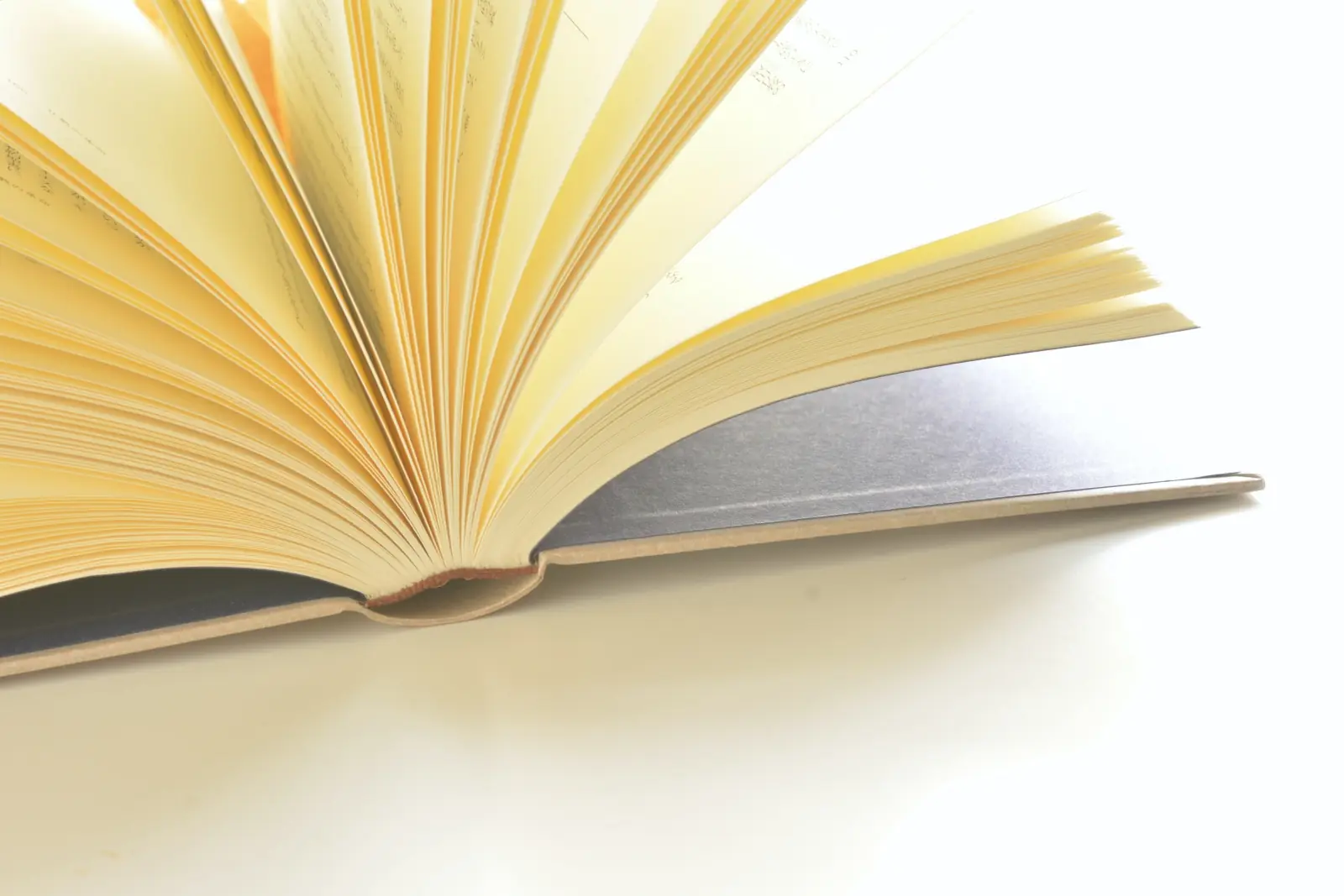
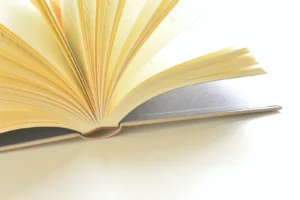


コメント