行政手続法の目的と「申請に対する処分」の意義
行政手続法は、行政運営における公正性の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定された法律である。
この法律は、行政の意思決定の内容と過程を国民にとって「見える化」することで、行政の恣意的な判断を抑制し、国民の行政に対する予測可能性を高め、信頼を確保するための基盤を構築することを目指している。
本法が対象とする主要な手続きは、「処分」「行政指導」「届出」「命令等」の4つであり、これらの手続きに関する共通事項を定める一般法としての性格を有している。
他の法律に特別の定めがある場合には、その特別法が優先されるという一般法の原則も明確に示されている。
「申請に対する処分」は、行政手続法第2章に規定されており、国民が法令に基づき行政庁に対し、許可、認可、免許など、自己に何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であり、これに対して行政庁が諾否の応答をすべきものとされている処分を指す 3。これは、国民が行政サービスや許認可を求める際の行政庁の対応を規律する、行政と国民の最も直接的な接点の一つである。この第2章の規定は、行政の公正性・透明性を確保し、国民の権利利益を保護する上で極めて重要な役割を担っている。
本章が目指す行政運営の公正性・透明性向上と国民の権利利益保護は、行政庁が申請に対して漫然としたり、恣意的な判断をしたりすることを抑制し、迅速かつ公正な処理を促すことにある 7。具体的には、審査基準の公表、標準処理期間の設定、理由の提示などを通じて、申請者が処分の見通しを立てやすくし、不服申立ての便宜を図ることで、国民の権利利益の実効的な保護を目指す。
行政手続法の目的として「公正の確保」と「透明性の向上」が掲げられており、特に「透明性」は「行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること」を指す。
これは単なる情報公開に留まらず、行政の意思決定プロセス自体を国民が理解し、予測できる状態を目指していることを示唆する。
申請に対する処分は、国民が行政に能動的に関わる最も一般的な接点であるため、この章の規定は、行政が一方的に決定を下すのではなく、国民との対話を通じて意思決定を行うという、より開かれた行政への転換を促している。
これにより、国民は行政サービスを享受する「受益者」であると同時に、行政の意思決定プロセスを監視し、その適法性・妥当性を問い得る「権利の主体」としての側面が強化される。
行政の「見える化」は、行政の「恣意性抑制」と国民の「予測可能性向上」という二重の目的を持つものであり、行政の裁量権の行使に行政手続法が一定の規律を課すことで、行政の権力行使の正当性を担保しようとする行政法の基本原理と深く結びついている。
この「見える化」の原則は、行政のデジタル化が進む現代において、電子申請やAIを用いた審査など、新たな技術が導入される際にも、そのプロセスが国民にとって理解可能で透明であるかどうかが、その制度設計の重要な評価軸となることを示唆している。
以下に、行政手続法第2章の主要条文の概要と法的性質をまとめた表を示す。
表1: 行政手続法 第2章 主要条文の概要と法的性質
| 条文 | 目的 | 内容 | 法的性質 |
| 第5条(審査基準) | 行政の恣意抑制、予測可能性向上 | 審査基準の策定・公表 | 策定・公表ともに義務(例外あり) |
| 第6条(標準処理期間) | 迅速化、透明性向上 | 標準処理期間の設定・公表 | 設定は努力義務、設定した場合の公表は義務 |
| 第7条(申請に対する審査、応答) | 遅滞なき審査、不備への適切対応 | 遅滞なき審査開始、形式不備への補正or拒否 | 審査開始は義務、補正or拒否は選択的 |
| 第8条(理由の提示) | 恣意抑制、不服申立て便宜 | 拒否処分時の理由提示 | 原則義務(例外あり)、書面性義務 |
| 第9条(情報の提供) | 透明性向上、申請者の不安軽減 | 審査進行状況・見通し、申請必要情報の提供 | 努力義務 |
| 第10条(公聴会の開催等) | 第三者利害の考慮、公正性確保 | 申請者以外の意見聴取 | 努力義務 |
| 第11条(複数の行政庁が関与する処分) | 不当な遅延防止、審査促進 | 他の申請を理由とする遅延禁止、行政庁間の連携 | 遅延禁止は義務、連携は努力義務 |
2. 第5条 審査基準の策定と公表
行政庁は、申請により求められた許認可等を行うかどうかを、その法令の定めに従って判断するために必要とされる「審査基準」を定めなければならないとされている。
この審査基準の策定は、行政の裁量権の行使を明確化し、恣意的な判断を防ぐための重要な要請である。
さらに、審査基準は、許認可等の性質に照らして、できる限り具体的なものとしなければならない。
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け、またはその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。この「その他の適当な方法」には、ウェブサイトでの公開なども含まれる。
公表義務の例外として「行政上特別の支障があるとき」が認められているが、これは限定的に解釈されるべきである。
審査基準を公にすることによって、申請者は自身の申請が許可されるかどうかの見通しを立てやすくなり、行政の判断の予測可能性が向上する 。また、審査基準の存在と公表は、行政庁が審査を行う際の判断の公正性・合理性を担保し、恣意的な判断を抑制する効果を持つ。
審査基準が「できる限り具体的」であるべきという要請は、行政の裁量権を完全に排除するものではなく、その行使の範囲と基準を明確化することで、裁量の濫用を防ぐという微妙なバランスを追求している。
過度に抽象的な基準では、行政の判断が依然として不透明になり、恣意性を招く恐れがある。一方で、あまりにも詳細に基準を定めすぎると、個々の事案が持つ多様な特性や、社会情勢の変化に柔軟に対応することが困難になり、硬直的な行政運用につながる可能性がある。
最高裁判所の判例、例えば「個人タクシー事件」では、行政庁が内部的に設定した審査基準を公正かつ合理的に適用することの重要性が強調されており、これはまさにこの具体性と裁量の間の緊張関係を示していると言える。
審査基準の具体性は、後の拒否処分における理由提示義務(第8条)と密接に関連している。
審査基準が明確かつ具体的であればあるほど、申請が拒否された際の理由提示もより具体的で説得力のあるものとなり、申請者が不服申立てを行う際の便宜が図られることになる。
審査基準の策定と公表は、行政の専門性と透明性を両立させるという現代行政の課題を内包している。
特に専門性が高い分野では、基準の具体的な数値化が難しい場合もあるが、それでも可能な限り客観的な指標を導入し、判断過程を説明可能にすることが、国民からの信頼を得る上で不可欠な要件となっている。
3. 第6条 標準処理期間の設定と公表
「標準処理期間」とは、行政庁が申請を受け付けてから(申請が事務所に到達してから)、許可・不許可の処分を下すまでに通常要すべき標準的な期間を指す。
行政庁は、この標準処理期間を定めるよう努めるものとされており、これは「努力義務」である。したがって、必ずしも設定しなければならない義務ではない点に留意が必要である。
しかし、標準処理期間を定めた場合は、必ず公にしなければならないという「義務」が生じる。
公表方法は、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付け、またはその他の適当な方法による。
また、法令により当該行政庁と異なる機関が申請の提出先とされている場合は、当該申請が提出先に到達してから行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間も定めるよう努めることとされている(任意)。
標準処理期間の設定と公表は、申請者にとって処分の時期の予測可能性を高め、行政処理の迅速化を促す効果がある。これは行政運営の適正化と透明性の向上に資するものであり、申請者が行政手続きの進行状況を把握する上での重要な目安となる。
標準処理期間の設定が「努力義務」である一方で、設定した場合には「公表義務」が生じるという規定は、行政の多様な業務や複雑な事案において一律に期間を定めることの困難さを考慮したものと考えられる。
しかし、単なる努力義務に留まるとその実効性が問われる可能性があるため、設定した場合には公表を義務付けることで、行政に対する外部からの監視を促し、迅速な処理へのインセンティブを与える構造になっている。
もし標準処理期間を超過した場合でも、行政手続法には直ちに処分を取り消す旨の規定はないが、申請者はその理由や見通しを求めることができる(第9条)。
これは、期間超過自体が違法となるわけではないが、行政には説明責任が課されることを示唆している。
標準処理期間の「努力義務」は、法的拘束力は弱いものの、行政の行動を一定の方向に誘導し、透明性を高める効果を狙っている。標準処理期間の運用は、行政の業務改善や生産性向上にもつながる可能性がある。期間を意識することで、内部プロセスの見直しや効率化が図られ、結果として国民サービスの向上に寄与することが期待される。
4. 第7条 申請に対する審査、応答の原則
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないという義務を負う。これは、申請者の待機期間を不当に長くしないための原則であり、行政処理の迅速な確保を目的としている。
申請書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること、申請期間内にされたものであることなど、法令に定められた「形式上の要件」に適合しない申請については、行政庁は、速やかに申請者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めるか、または申請を拒否しなければならないという選択的義務を負う。行政庁は、補正を求めることなく、直ちに拒否処分を行うことも可能である。
「遅滞なく審査を開始しなければならない」という規定は、申請者の権利行使を不当に阻害しないための行政庁の義務である。
この「審査」には、まず申請の形式的な要件(記載漏れ、添付書類の有無、申請期間内かなど)の確認が含まれる。
形式審査の結果、不備があれば補正を求めるか拒否処分をするという選択肢が行政庁に与えられている。
この選択肢は、行政の効率性と申請者の利便性のバランスを図るものであり、行政が不完全な申請に漫然と対応することを防ぎつつ、不必要な拒否処分を避けるための柔軟性を提供している。
形式上の不備に対する「補正」の選択肢は、行政指導(特に申請に関連する行政指導、第33条)と一部重なる側面を持つが、第7条は法的義務としての補正要求または拒否を定めている点で異なる。
行政指導は任意性が原則であるのに対し、第7条の対応は行政庁に課された法的義務である。
5. 第8条 拒否処分における理由の提示
行政庁は、申請により求められた許認可等を「拒否する処分」をする場合、原則として、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならないという義務を負う。拒否処分を書面でするときは、その理由も書面により示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載または添付書類その他の申請の内容から「明らかであるとき」は、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りるという例外が設けられている。
この例外は、理由が極めて明白な場合に、行政の事務負担を軽減しつつ、申請者の権利保護を損なわないための措置である。
理由提示は、処分庁に行政判断の慎重性・合理性を担保させ、その恣意を抑制する機能を持つ。また、処分の理由を相手方に知らせることで、申請者が行政不服審査法に基づく審査請求などの不服申立てをする際の便宜を図るという重要な機能がある。
理由が不明確であれば、申請者は不服申立ての手続きを手探りで始めなければならず、権利の実効的な行使が困難になる。
理由提示の程度は、処分の根拠法令、処分基準の有無・内容・公表状況、処分の性質、原因となる事実関係などを総合考慮して決定される。最高裁判所の「個人タクシー事件」判例(最判昭和46・10・28)は、審査基準の公正かつ合理的な適用と、これに反する審査手続きによる却下処分が違法となることを示した。
また、「一級建築士免許取消事件」判例(最判平成23・6・7)は、不利益処分における理由提示として、処分の原因となる事実、根拠法条に加え、処分基準の適用関係まで示す必要があるとし、これが不十分であれば違法となると判断した。
この判例は、理由提示が不備である場合、処分が「一発取消し」となるという判例法理を強調している。
理由提示は、単に拒否された事実を伝えるだけでなく、なぜ拒否されたのか、その法的・事実的根拠を明確にすることで、行政の判断が恣意的でないことを担保し、申請者が次の行動(再申請、不服申立て等)を検討するための情報を提供する。
判例が理由提示の具体性を厳しく求めるのは、この実質的意義(行政の自己規律と国民の権利保障)を重視しているためである。特に、裁量権の行使を伴う処分においては、行政がどのような考慮要素に基づいて判断したのかを示すことで、その裁量行使の適法性・妥当性が検証可能となる。
理由提示の義務は、行政の「公正性」と「透明性」を具体的に担保する最も重要な条文の一つである。
審査基準(第5条)が事前に「透明性」を提供するのに対し、理由提示(第8条)は事後に具体的な判断の「公正性」を検証可能にする。
理由提示の不備が処分の違法事由となり得るという判例法理は、行政実務において、理由提示の重要性を強く認識させ、その内容の充実に努めるインセンティブを与えている。これは、行政庁が単に結論を示すだけでなく、その過程と根拠を論理的に説明する能力が求められることを意味する。
以下に、拒否処分における理由提示の原則と例外をまとめた表を示す。
表2: 拒否処分における理由提示の原則と例外
| 項目 | 内容 | 関連条文/機能 |
| 原則 | 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならない。 | 行政手続法第8条第1項本文 |
| 書面性の原則 | 原則に規定する処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければならない。 | 行政手続法第8条第2項 |
| 例外 | 法令に定められた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載または添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 | 行政手続法第8条第1項ただし書き |
| 理由提示の機能 | 行政庁の恣意的な判断を抑制し、判断の慎重性・合理性を担保する。申請者が不服申立てを行う際の便宜を図る。 | 行政手続法第8条の立項趣旨 |
6. 第9条 情報の提供
行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。これは「努力義務」であり、行政庁に絶対的な義務を課すものではないが、申請者の不安を軽減し、手続きの透明性を高めるための配慮規定である。
また、行政庁は、申請をしようとする者または申請者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
第9条の規定は、いずれも行政庁の「努力義務」である。これは、行政の業務負荷や予見可能性の限界を考慮しつつも、国民の行政に対する期待に応え、行政サービスの質を向上させるための「ソフトロー」的な役割を果たす。
審査の進行状況や処分の見通しを伝えることは、申請者の時間的・精神的負担を軽減し、行政に対する信頼感を醸成する。また、申請に必要な情報の提供は、申請段階での不備を減らし、行政側の審査効率向上にも寄与する。
第9条の「情報の提供」は、第5条の「審査基準の公表」や第6条の「標準処理期間の公表」と相まって、行政手続き全体の「透明性」を多角的に高める役割を担う。
事前情報(基準・期間)と途中経過情報(進行状況・見通し)が連携することで、申請者はより包括的に行政プロセスを把握できるようになる。
7. 第10条:公聴会の開催等
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
これは「努力義務」であり、必ずしも公聴会を開く必要はない。
公聴会は、例えば原子力発電所の原子炉設置許可のように、特定の申請に対する処分が申請者以外の第三者(周辺住民など)の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合に、その意見を聴取し、行政の意思決定の公正性と客観性を高めることを目的とする。不利益処分の場合とは異なり、申請に対する拒否処分の場合に公聴会開催が義務付けられているわけではない。
第10条は、申請者自身の利益だけでなく、その処分が第三者の利害に影響を及ぼす可能性がある場合に、行政がその第三者の意見を聴取する機会を設ける努力義務を課している。
公聴会は、この多角的な利害を可視化し、行政の意思決定に反映させるための重要なプロセスであり、行政の決定がより公共的な正当性を持つことを可能にする。
公聴会は、行政の意思決定プロセスにおける「参加」の機会を提供するものであり、行政の「透明性」と「公正性」を強化する。
これは、行政手続法全体の目的である国民の権利利益保護を、申請者だけでなく、その処分によって影響を受ける可能性のある第三者にまで拡張しようとする趣旨と合致する。
大規模開発や環境影響評価など、社会的に影響の大きい許認可においては、公聴会の開催が事実上不可欠なプロセスとなり、行政の意思決定の質を高める上で重要な役割を果たす。
8. 第11条:複数の行政庁が関与する処分
行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって、自らすべき許認可等をするかどうかについての審査または判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。これは、行政の縦割りによる不当な遅延を防止し、申請者の迅速な権利実現を保障するための規定である。
また、一の申請または同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行うなどにより審査の促進に努めるものとされている。これは、複雑化・広域化する行政事案において、複数の行政庁が連携し、効率的な処理を行うことを促すための規定である。
第11条は、複数の行政庁が関与する複雑な申請において、行政の「縦割り」構造が原因で生じる不当な遅延を防ぎ、行政庁間の連携を促すことを目的としている。
これは、申請者が複数の行政庁に個別に申請し、それぞれ異なる審査プロセスを経ることで生じる負担や非効率性を軽減し、実質的な「ワンストップサービス」に近い状態を実現しようとする行政の現代的な課題意識を反映している。
行政庁間の連携は努力義務ではあるものの、その推奨は、行政の効率性と国民の利便性の向上という、行政手続法全体の目的に合致する。
9. 「申請に対する処分」の適用除外
行政手続法は、全ての行政活動に一律に適用されるわけではなく、特定の処分や行政指導については適用除外が定められている。特に、地方公共団体がする処分については、その根拠が「条例または規則」に置かれているものに限り、行政手続法の規定は適用されない。しかし、法律に根拠を置く地方公共団体の処分には適用される。地方公共団体がする行政指導は、根拠規定に関わらず全て適用除外となる。
その他の適用除外の類型としては、国会・地方議会の議決による処分、裁判に関する処分、刑事事件・税金・金融商品取引の犯則事件に関する処分・行政指導、教育関係、公務員関係、外国人関係、利益相反の裁定、警察官等が現場でする処分・行政指導、情報収集のための処分・行政指導などが挙げられる。
これらの適用除外は、各分野の特殊性や迅速性・専門性の要請、あるいは既に別の法規で手続が定められていることなどを理由とする。
行政手続法に多くの適用除外規定が存在する。
これらの除外は、各行政分野の特殊性(例:刑事事件の迅速性、教育の専門性)や、既に特別法で手続が詳細に定められていること(例:税務)、あるいは行政の内部的な行為であることなどを理由としている。しかし、これらの除外規定があるからといって、行政が恣意的な行為を許されるわけではない。
むしろ、行政手続法の一般原則(公正性、透明性、国民の権利利益保護)は、適用除外の分野においても、個別の法令や解釈を通じて、その精神が尊重されるべきであるという暗黙のメッセージが込められている。
地方公共団体に関する適用除外の複雑さ(根拠が条例・規則か法律かによる違い)は、国と地方の権限配分、および地方自治の本旨という憲法上の原則との調整を示唆している。
適用除外が多いことは、行政手続法が「一般法」であることの限界を示す一方で、行政の多様な実態に柔軟に対応しようとする立法者の意図も反映している。しかし、国民から見れば手続きの複雑さにつながるため、各分野で法の精神に沿った運用が求められる。
以下に、行政手続法第2章の適用除外(地方公共団体関連)をまとめた表を示す。
表3: 行政手続法 第2章の適用除外(地方公共団体関連)
| 行政行為の種類 | 根拠規定 | 適用関係(行政手続法 第2章) |
| 地方公共団体の機関がする処分 | 条例又は規則に置かれているもの | 適用除外 |
| 法律に置かれているもの | 適用される | |
| 地方公共団体の機関がする行政指導 | 根拠規定に関わらず全て | 適用除外 |
| 地方公共団体の機関に対する届出 | 条例又は規則に置かれているもの | 適用除外 |
| 地方公共団体の機関が命令等を定める行為 | 根拠規定に関わらず全て | 適用除外 |
引用文献 (アクセスは記事公開時点)
- 総務省|行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)|行政手続法Q&A
- 行政手続制度に基づく審査基準等の公表について/大和町
- 行政手続法の逐条解説
- 行政手続について|流山市
- 行政手続に関する事務の手引
- 行政手続制度のあらまし/千葉県
- 行政手続法 事務取扱ガイドライン (Ver.1) 令和6年3月 総務省行政管理局
- 行政不服審査法の概要 | 総務省
- Ⅰ.申請に対する処分 Ⅱ.不利益処分 Ⅲ.理由の提示の諸問題
- 行政手続法第8条 – Wikibooks
- 標準処理期間の設定等要領
- 処分理由提示制度の目的・機能について
- 行政手続法第5条 – Wikibooks
- 行政手続法第9条 – Wikibooks
- 行政手続法9条:情報の提供
- 行政手続法第10条 – Wikibooks
- 行政手続法10条:公聴会の開催等
- 行政手続法第11条 – Wikibooks
- 衆議院 法律第八十八号(平五・一一・一二)
- 行政手続法 | e-Gov 法令検索
- 32 Ⅸ.情報公開法第八条(行政文書の存否に関する情報) 第八条 開示請求に対し
- 八潮市, Ⅲ 標準処理期間
- 行政手続制度の概要 – 下関市
- 行政手続法33条:申請に関連する行政指導
- 行政指導とは?行政処分との違い・従わない場合・具体例・行政手続法のルール・受けた場合の対処法などを分かりやすく解説!
- 豊明市 行政手続法Q&A
- 大阪市行政手続条例 解釈・運用の手引
- 衆議院, 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
- 行政手続法3条:適用除外
- 行政手続法の逐条解説 (全条文の解説)
- 行政手続 – mahora
- 近畿管区行政評価局| 情報公開法、行政手続法及び行政不服審査法についての情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 – e-Gov 法令検索
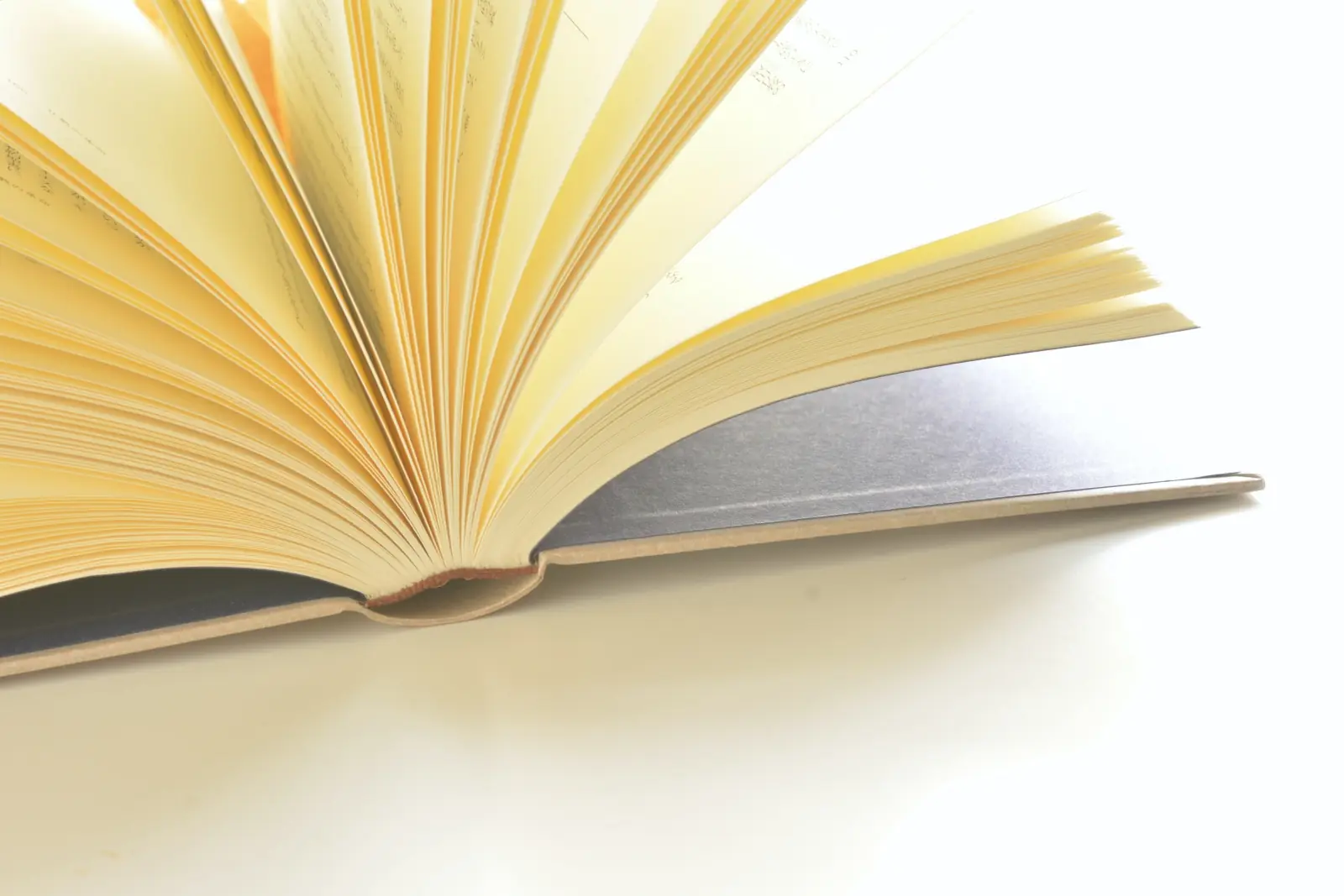
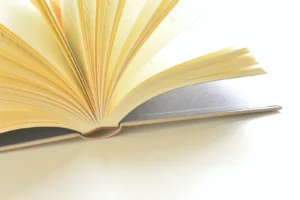


コメント