はじめに
地方公共団体における会計管理者は、その財務会計制度において極めて重要な役割を担っています。
会計管理者の職務は、財務行為における「決定権限」を長に、そして「執行権限」を会計管理者に分離することで、相互監視機能を制度的に組み込むことにあります。この権限分離は、単に不正行為を防止するだけでなく、地方自治体の財政健全性を確保する上で戦略的な意味合いを持ちます。長による財政決定が、たとえ善意に基づくものや緊急性を要するものであったとしても、会計管理者による法令や予算への適合性に関する厳格な審査を経なければならない仕組みが強制されます。この機能により、会計管理者の役割は単なる事務的な執行者にとどまらず、財政規律と公衆の信頼への遵守を保証する重要なゲートキーパーへと位置づけられます。これは、違法な行為を防ぐだけでなく、公衆の利益に沿った「適切」かつ「慎重」な財政運営を確保することにも直接的に寄与します。したがって、会計管理者の存在は、地方自治体全体の財政健全性と公衆の信頼を確保する上で不可欠な要素となっています。
会計管理者の概要
会計管理者とは(地方自治法第168条)
会計管理者とは、地方公共団体の会計事務を統括する人物です。地方自治法第168条に基づき、全国の普通地方公共団体(都道府県、市町村)に必ず1人置かれる必置の役職とされています。会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員の中から、長が任命します。その身分は、特別職ではなく、一般職の地方公務員として扱われる点が特徴であり、長の任命に際して議会の承認を得る必要はありません。
会計管理者の職務と権限
主要な職務内容(地方自治法第170条)
会計管理者は、地方公営企業の会計事務を除く、当該地方公共団体の全ての会計事務をつかさどります。その職務は多岐にわたります。
具体的には、以下の職務を担います
- 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管を行うこと。
- 小切手を振り出すこと。
- 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む)の出納及び保管を行うこと。
- 物品(基金に属する動産を含む)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)を行うこと。
- 現金及び財産の記録管理を行うこと。
- 支出負担行為に関する確認を行うこと。
- 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
これらの職務を補助するため、会計管理者の下には出納員その他の会計職員が置かれます。また、長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則によって必要な組織を設けることができます。
長(首長)との役割分担と相互監視機能
地方公共団体の財務行為に関する最終的な執行権限は長にありますが、地方自治法の規定により、その一部の権限が会計管理者に委任されています。
長の権限(地方自治法第149条2号から7号)は以下の通り
- 予算を調製し、及びこれを執行すること。
- 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
- 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
- 会計を監督すること。
- 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
- 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
会計管理者は、長の補助機関である職員という位置づけでありながら、会計事務の執行においてはその独立性を保つことが法的に定められています。
支出負担行為の確認義務と財務執行プロセス
会計管理者の職務の中でも特に重要なのが「支出負担行為に関する確認」です。会計管理者は、長の政令で定めるところによる命令がなければ支出を行うことができません。さらに、支出命令を受けた場合であっても、当該支出負担行為が法令または予算に違反していないこと、および債務が確定していることを確認した上でなければ支出を行うことができません。
この確認義務は、財務行為の適法性・適正性を確保するための極めて重要な措置です。会計管理者の確認義務は、長の財務決定(支出負担行為)が最終的な「支払い」に至る前の最後の砦となります。これは、長の決定がたとえ政治的な意図や緊急性を帯びていたとしても、それが法令や予算に適合しているか、債務が確定しているかという客観的な基準で判断されることを意味します。会計管理者がこの確認を怠れば、違法・不当な支出が発生し、公金が不適切に流出するリスクが高まります。したがって、会計管理者は、長の暴走や誤りを防ぎ、公金を保護する「守りの要」としての極めて重要な機能を果たしています。
歳入についても、会計管理者はその適正性を確保する役割を担います。具体的には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか、その他法令または契約に違反する事実がないか等を調査して調定を行います。
会計管理者の職務内容一覧
| 職務内容 | 根拠条文(地方自治法第170条) | 説明 |
| 現金の出納及び保管 | 第170条1項1号 | 地方公共団体の現金を適切に受け入れ、支払い、安全に保管する。現金に代わる証券や基金に属する現金も含む。 |
| 小切手の振り出し | 第170条1項2号 | 地方公共団体の支出のために小切手を発行する。 |
| 有価証券の出納及び保管 | 第170条1項3号 | 公有財産や基金に属する有価証券を適切に受け入れ、支払い、保管する。 |
| 物品の出納及び保管 | 第170条1項4号 | 基金に属する動産を含む物品の受け入れ、払い出し、保管を行う(使用中の物品は除く)。 |
| 現金及び財産の記録管理 | 第170条1項5号 | 地方公共団体の現金および全ての財産の状況を正確に記録し、管理する。 |
| 支出負担行為に関する確認 | 第170条1項6号 | 長からの支出命令に対し、その支出が法令や予算に適合していますか、債務が確定していますかを確認する。 |
| 決算の調製と提出 | 第170条1項7号 | 会計年度の決算書を作成し、長の承認を得て議会に提出する準備を行う。 |
会計管理者の法的地位と独立性
身分保障と任命要件(一般職としての位置づけ)
会計管理者は、地方自治法に基づき、特別職ではなく一般職の地方公務員として位置づけられています。一般職の地方公務員は、地方公務員法によって手厚い身分保障が与えられています。具体的には、勤務実績不良、心身故障による職務遂行困難など、法律または人事院規則に定める場合を除き、本人の意に反して降任、休職、または免職されることはありません。
会計管理者は、長がその補助機関である職員の中から1人を選んで任命します。この任命に際しては、議会の承認は不要です。
会計管理者の「一般職」としての身分保障は、彼らが長の政治的圧力や不当な介入から保護され、法令と予算に厳格に従って職務を遂行できる「職務遂行上の独立性」を質的に向上させる効果があります。この身分保障は、単に「職を失わない」という消極的な独立性だけでなく、違法・不当な指示に対して「ノー」と言える積極的な独立性を担保します。例えば、長から不適切な支出命令があった場合でも、身分保障があるからこそ、会計管理者はその命令を拒否し、法令遵守を優先することができ、これにより、会計管理者は、財務の適正性を確保するための「最後の防波堤」としての役割を、より強固に果たすことが可能となります。
親族関係による就任制限(地方自治法第169条)
会計管理者の独立性と公正性を確保するため、地方自治法第169条には厳格な親族関係による就任制限が設けられています。具体的には、普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、または監査委員と、親子、夫婦、または兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができません。
この関係が会計管理者の就任後に生じた場合でも、その職を失うこととされています。
この親族関係制限は、単なる不正防止策に留まりません。会計管理者が長の補助機関でありながら、その職務の性質上、長やその側近、あるいは監査機能を担う監査委員との間に、私的な利害関係が生じることを排除するものです。もし親族関係が許されれば、不正の隠蔽や不適切な支出が容易になり、住民の不信を招くことになります。この規定は、制度設計における「性悪説」に基づいた、強力な牽制機能として機能しています。
会計管理者の責任と判例
損害賠償責任(地方自治法第243条の2)
地方自治法第243条の2第1項前段は、会計管理者の損害賠償責任について定めています。この規定に基づき、会計管理者が故意または過失により保管に係る現金を亡失した場合、その損害について賠償責任を負います。
職務執行に関する主要判例の考察
最高裁判所判例 昭和63(行コ)26. 平成2年4月26日(最高裁平成3年12月20日判決)
この判例は、地方公営企業の管理者が、自身の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させていた状況下で、その補助職員が違法な財務会計行為を行った場合の管理者の責任が問われた事案です。
- 判示事項:
- 自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者も、地方自治法第242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当する。
- 補助職員に専決処理させた場合であっても、管理者は、補助職員が違法な財務会計行為を行うことを防止すべき指揮監督義務に違反し、故意または過失によりこれを防止しなかった場合に限り、普通地方公共団体が被った損害に対する賠償責任を負う。
この判例は、会計管理者(またはそれに準ずる財務責任者)が、たとえ実務を補助職員に任せていたとしても、その指揮監督義務を怠れば、最終的な賠償責任を免れないことを示しています。これは、権限の委譲があっても、責任は上位者に帰属するという原則を確立したものです。
不祥事事例と再発防止策
御杖村公金横領事件(平成30年発覚)
御杖村の元会計管理者が、平成28年4月1日から平成30年10月1日までの2年6ヶ月にわたり、巧妙な手口で公金約400万円を横領した事件です。
手口
- 現金出納簿に架空の現金支払いを記入し、その金額を横領した。
- 現金出納簿の日時集計を意図的に低く改ざん記載し、その差額を横領した。
- 金銭出納簿の税金等の収入を実際の金額より低く改ざん記帳し、その差額を横領した。
- 小切手を発行し、その現金を現金出納簿の収入欄に記載せず横領した。
- 横領発覚を避けるため、基金口座から会計管理者口座への不正な資金移動(穴埋め)や、決算における基金残高の改ざんを行った。
責任
元会計管理者は、地方自治法第243条の2第1項前段に基づき、故意による公金亡失として損害賠償責任を負うと認定された。
まとめ
地方自治法における会計管理者制度は、地方公共団体の財務会計における公正性、透明性、効率性を確保するための重要な基盤です。この制度は、長の財務行為に対する独立したチェック機能を担い、公金の適正な管理を担保することで、住民の信頼を維持・向上させる上で不可欠な存在となっています。
出典(2025年6月13日アクセス)
- 総務省 ・ 地方自治法第9章(財務)の概説に ついて(説明案件)
- 会計管理者 – Wikipedia
- e-Gov 法令検索,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
- 現行の財務会計制度の適正性等を担保するための措置
- 衆議院 地方自治法の一部を改正する法律
- 財政用語の説明 | 岩倉市
- 収入役 – Wikipedia
- 政府の行政改革 我が国の国家公務員制度の概要
- 地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン(たたき台)のポイント 適正な
- 総務省 地方公共団体における内部統制制度の 導入・実施ガイドライン 平成 31 年3月 (令和6年3月
- 社内不正防止の仕組み作り
- 御杖村 公金横領による元職員の賠償責任等に関する監査請求に基づく監査の結果について
- 総務省 地方財務会計制度の課題と見直しの方向性ついて
- 会計監査を行う目的や監事が確認すべき点について
- 裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
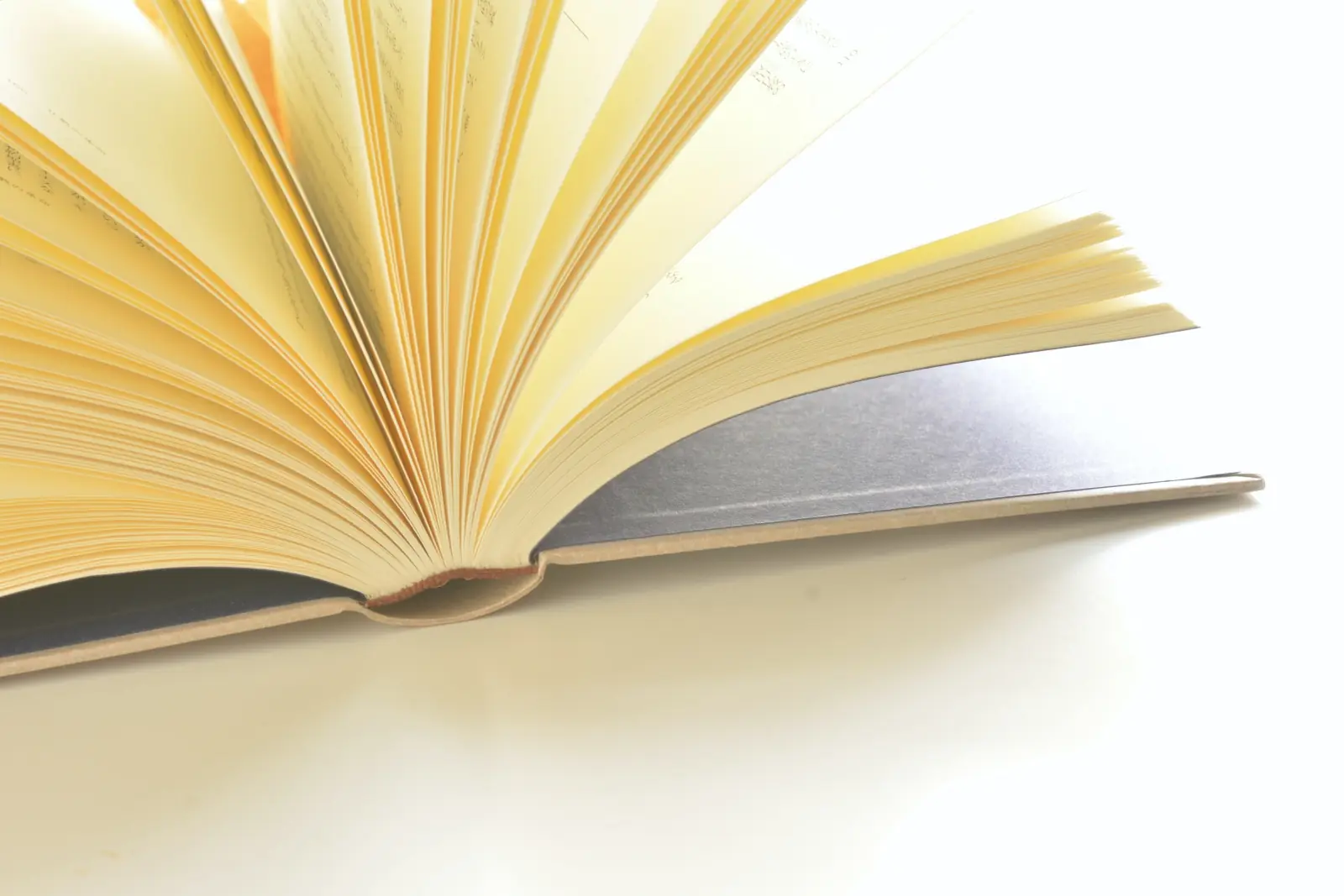
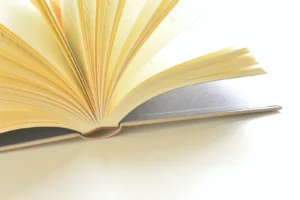


コメント